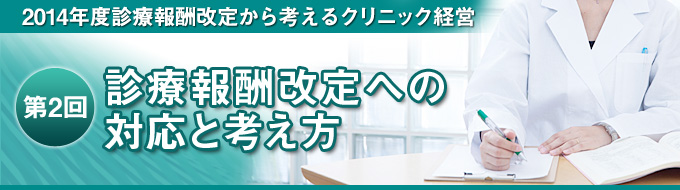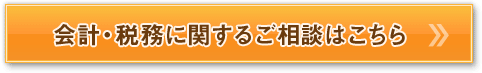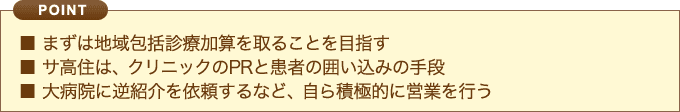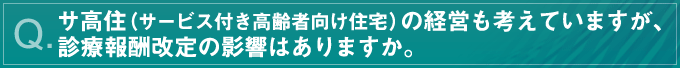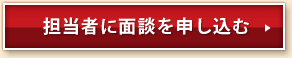特集記事アーカイブ
 経営情報
経営情報
2014/05/08 2014年 診療報酬改定への対応と考え方
前回は、診療報酬改定の方向性に関してお伝えしましたが、今回は対応と考え方についてお伝えします。
2014年度の診療報酬改定は、極めてインパクトの大きいものです。超少子高齢社会の医療ニーズに合わせた体制を構築するための、まさしく変革への第一歩となりました。その影響と対応について考察します。

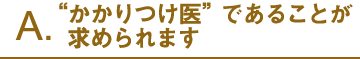
クリニックは、地域に密着した主治医の機能、すなわち「かかりつけ医」であることが強く求められています。今回の改定においても、新設された「地域包括診療料・同加算」が目玉の一つとなっています。
これは、高血圧、糖尿病、脂質異常、認知症の4疾病のうち2つ以上有する患者を対象に、継続的・全人的な医療を行うことに対するものです。
主治医機能の評価を受ける条件として、在宅医療の提供や24時間対応をしている薬局と連携していること、介護保険に係わる相談を受けていることなどがあげられます。
主治医機能の評価算定の準備として、以下に <1>カルテ記載要件 および、<2>院内掲示要件 を示しました。
| (1) | 医師はお薬手帳のコピーをカルテに貼付する |
| (2) | 健康診断・検診の受診勧奨を行いその結果等をカルテに記載 |
| (3) | 他の医療機関と連携の上、患者がかかっている医療機関をすべて把握するとともに、 処方されている医薬品をすべて管理し、カルテに記載 |
<2> 院内掲示要件
| (1) | 健康相談を行っていること |
| (2) | 介護保険に係わる相談をおこなっていること |
| (3) | 在宅医療の提供及び24時間の対応を行っていること |
これから医院開業を検討される先生は、診療所のみが算定できる地域包括診療加算が算定できるようにすべきでしょう。地域包括診療料に比べて在宅医療の提供および24時間の対応等について要件が緩やかになっています。
高齢者住宅や有料老人ホームなどを舞台にマージンをとって在宅患者を紹介する不適切な事例が問題視されました。適正化への対策として、在宅時医学総合管理料などで、同一建物への訪問の場合には大幅な減額がされました。この取り扱いはサービス付高齢者向け住宅の普及に関しても影響が考えられ、「病院から在宅へ」の流れを止めることが危惧されます。しかし、月2回以上の訪問診療のうち最低月1回は単独で訪問診療を行うことで在宅時医学総合管理料の算定ができます。スケジュールに基づいて訪問診療を実施することにより減額のない対応が可能となります。
また、大都市圏で高齢者の単身世帯が増えていく中、サ高住への需要は高くなる一方です。地域の需要を冷静に見極め、介護度の高低など、ニーズに合致したサ高住を提供できれば利益は確保できる可能性はあります。また、サ高住の経営をしているということで、地域に対するPR効果と患者の囲い込みも期待できるでしょう。

これまで見てきたように、今回の診療報酬改定のインパクトは大きく、医療経営の在り方を根本から考え直す必要があります。
しかし、とらえ方によって逆境はチャンスにもなります。
例えば、病院とクリニックの機能分化により、病院はより急性期医療の色が強くはたらきます。自クリニックがかかりつけ医として、(1) どんな患者の受け入れが可能か? (2) 在宅は可能か? (3) リハビリは可能か? (4) 化学療法は可能か? (5) どんな機能を持っているのか? (6) どんなスタッフ(専門医・リハビリ)がいるのか? (7) どのような特徴があるのか?など大病院が逆紹介したくなるような情報を発信しましょう。情報発信することで患者の囲い込みが期待できるのです。
〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台9-29-3 大山ビル 代表者 大山 哲
医療経営のスペシャリストとして認知され、数多くの医療機関の成長発展をバックアップしています。
無駄は抑えて、キャッシュフロー経営を
合法的な節税は資産形成に有効な手段ですが、しかし、節税が第一の目的になってしまうと無駄な支出が増えてしまいます。医療経営に重要なのは、まずキャッシュフローを考えて利益を増やすことです。後継者育成にもお金がかかります。無駄な支出を抑えて、キャッシュフローの改善を考えながら経営にあたることをお勧めします。
<発行書籍のご案内>

中小企業再生への改善計画・銀行交渉術 [単行本(ソフトカバー)]
中村 中 (著), 仁木 淳二 (著), 大山 哲 (著) 発行:2013年5月1日 ISBN:978-4-324-09665-9 出版:ぎょうせい |

税理士・公認会計士のための医業経営コンサルティング [単行本]
大山 哲 (著) 発行:2013年9月26日 ISBN:978-4-433-53183-6 出版:清文社 |
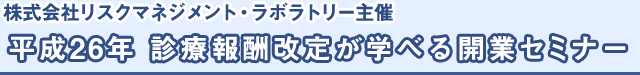
クリニック開業について何から手をつけて良いのか、場所はどこにすれば良いか、どのくらい期間が必要なのか、自己資金はどのくらい必要なのか ・・・
実際のクリニックの例を見ながら、実態に即した開業計画書はどういうものか、ご自身がどのようなクリニックを開業したいのか学びます。
※それぞれの事務所の対応エリアに関しては、詳細ページをご参照ください。