特集記事アーカイブ
 経営情報
経営情報
2015/12/03 診療報酬改定と医院経営への影響

開業医は、医師と経営者の両側面を持ち合わせている必要があるでしょう。特に経営者の視点に立った時、2年に1度の診療報酬改定は医院経営にとって非常に大きな影響があります。病院からの給与報酬だった勤務医時代にはそこまで確認していなかった診療点数が、開業医になると自身の収入にも関わってくるためです。
2016年4月改定の焦点は、診療報酬が「引き上げられるか」「引き下げられるか」という点でしょう。過去3回(2010年、2012年、2014年)の改定時には診療報酬は引き上げられましたが、メディアで既報の通り、政府は増え続ける社会保障費を抑える方針を打ち出しており、次回の改定では8年ぶりに診療報酬が引き下げられるかが注目されていいます。また2017年の消費税増税を考慮すると、これまで以上に医院の経営環境は厳しくなることが予想されます。
今後の予定としては年内には改定率が判明し、その後は中医協(中央社会保険医療協議会)にて個別に検討が行われる予定です。前回は在宅医療を推進する方向から、「地域包括診療料・同加算」が新設されるなど、新たな算定方法が示される場合もある。自身が提供する予定の医療に関わる診療報酬がどのように変わるのか、引き続き当局の決定を注視する必要があります。
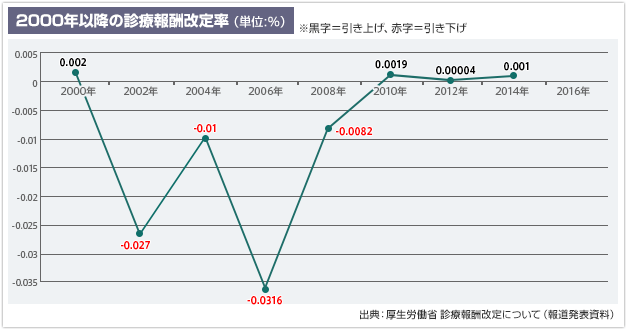
診療報酬改定によって影響を受けるポイントとして何といっても大きいのは、医業収入が変わることだ。ご存知のように、診療報酬は初診料・再診料といった基本診療料と、各種の検査や処置などによって加算される特掲診療料の合計で計算される。
医療機関の月収を簡単に表すと、
月収=平均診療単価×1日当たりの患者数×診療日数
この計算の前提となる平均診療単価が変わることは、どの程度インパクトがあるのだろうか。例えば1日当たりの患者数が100人、月の診療日数が22日とすると、平均診療単価が1点分(10円)下がっただけで、1カ月あたり22,000円の減収になる計算だ。1年間に換算すればいかに大きな金額か想像できるだろう。
仮に診療報酬が引き下げられれば、収入の落ち込みをカバーするために患者を増やす取り組みを積極的に行う、診療日を増やすなどの施策が必要になってくる。ただ、平均診療単価は診療科目によって差があるだけでなく、診療科によっては診察する患者数を単純に増やすことが物理的に困難な場合もある。そうなれば固定費などのコスト削減を検討しなければならないだろう。

