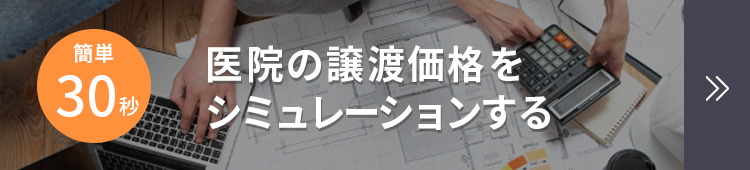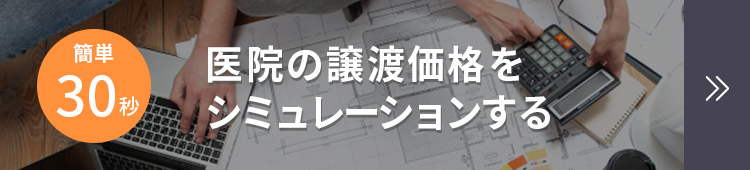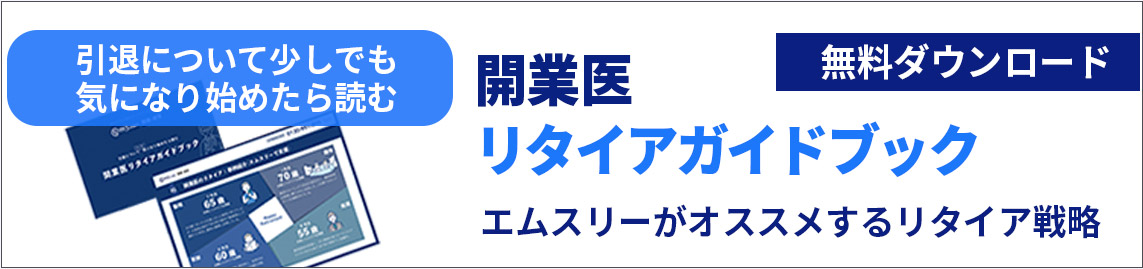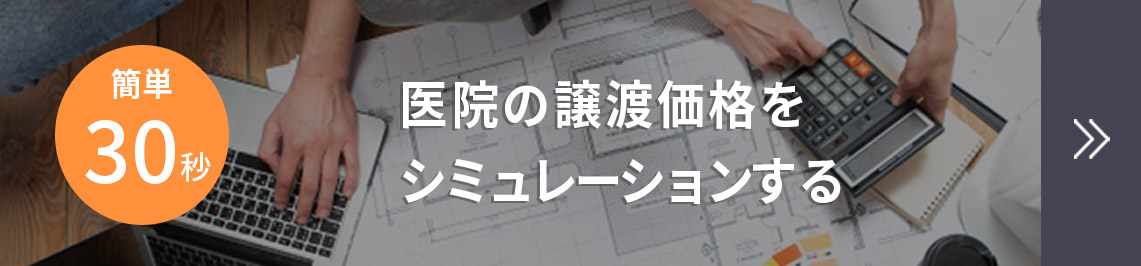2026年度診療報酬改定の動向と医院継承への影響:開業医が知るべきポイントと成功戦略
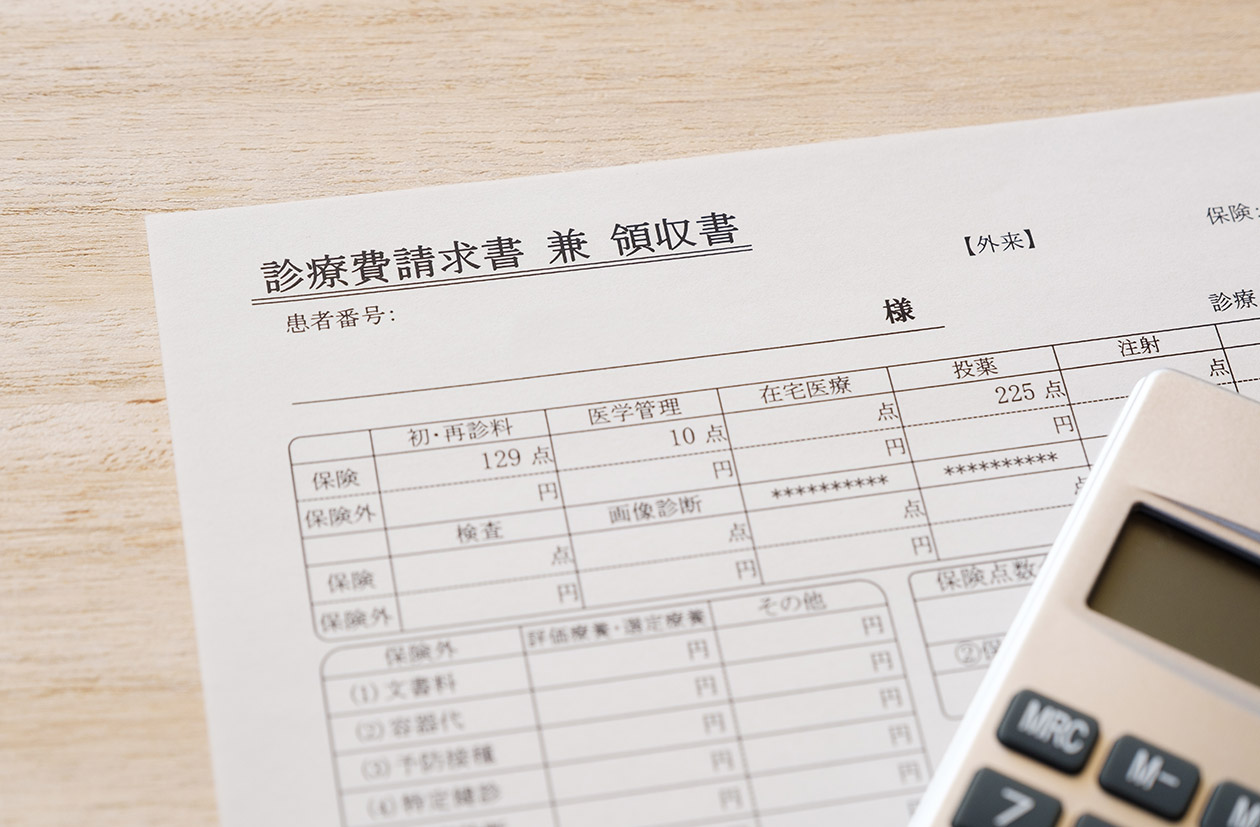
はじめに:診療報酬改定と医院経営の未来
「日々の診療に手一杯で、診療報酬改定の情報収集まで手が回らない」「次回の改定で、自分のクリニックの経営はどうなるのだろうか?」そうお悩みの開業医の先生方も少なくないのではないでしょうか。診療報酬改定は、クリニックの経営に直接影響を与えるだけでなく、先生方のリタイアプランや医院継承の成否をも左右する重要な要素です。
2年に一度行われる診療報酬改定は、医療機関の収入構造を大きく変える可能性を秘めています。特に、高齢化社会の進展や医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進など、日本の医療を取り巻く環境が大きく変化する中で、改定の内容は年々複雑化し、その影響は多岐にわたります。
本記事では、過去の診療報酬改定のトレンドを振り返りつつ、2026年度の改定見通しと、それが医院継承にどのような影響を与えるのかを詳細に解説します。さらに、診療報酬改定を見据えた上で、先生方が理想的なリタイアを実現し、大切な医院を次世代に引き継ぐための具体的な戦略についてもお伝えします。
地域医療を長年支えてこられた先生方が、安心してセカンドキャリアに進むための一助となれば幸いです。
1.過去の診療報酬改定から読み解くトレンドと影響
診療報酬改定は、国の医療政策の方向性を色濃く反映しています。過去の改定を分析することで、将来のトレンドや、それが医院経営に与える影響を予測することができます。
1-1. 診療報酬改定の基本的な考え方と流れ
診療報酬改定は、厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)で議論され、答申された内容に基づいて行われます。主な改定の柱としては、以下の3点が挙げられます。
(1)地域包括ケアシステムの推進と在宅医療・訪問看護の評価
超高齢社会を迎え、住み慣れた地域で医療・介護を受けられる「地域包括ケアシステム」の構築が喫緊の課題となっています。これに伴い、在宅医療や訪問看護の診療報酬上の評価が強化されてきました。
- 影響
在宅医療への移行や、他施設との連携が促進され、外来診療中心のクリニックでも、地域連携の重要性が増しました。一方で、在宅医療への新規参入には、人材確保や多職種連携のノウハウが必要となるため、経営戦略の見直しを迫られるクリニックも多く見られました。
(2)医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
オンライン資格確認の導入、電子処方箋の普及、医療情報の共有など、医療分野におけるデジタル化が急速に進められています。これらは、患者の利便性向上や医療の質の向上、業務効率化を目指すものです。
- 影響
医療機関には、オンライン資格確認システムの導入や電子カルテの更新など、IT投資が求められました。導入に際しては補助金制度なども設けられましたが、初期投資や運用コスト、スタッフの慣れなど、クリニックにとっては新たな負担となる側面もありました。しかし、長期的には業務効率化や情報連携の強化によるメリットが期待されています。
(3)働き方改革への対応
医師の働き方改革、特に医師の労働時間上限規制の導入に向けて、医療機関のタスク・シフト/シェアやICT活用による業務効率化が推進されてきました。
- 影響
務医を抱える病院だけでなく、将来的に医師を雇用する可能性のあるクリニックにおいても、労働環境の整備や業務効率化の意識が高まりました。これは、後継者がクリニックを継承する際にも、働きやすい環境が整備されているかどうかが判断材料の一つとなることを示唆しています。
(4)特定疾患管理料の見直しと生活習慣病への対応
生活習慣病の重症化予防や合併症対策への重点化が進められ、特定疾患管理料の算定要件や指導内容が見直されることがありました。
- 影響
患者への継続的な指導や多職種連携がより重視されるようになり、クリニックの診療内容や患者管理体制の質が問われるようになりました。
これらの過去の改定トレンドは、単なる点数改定に留まらず、医療機関のあり方そのものに変革を促すものでした。そして、この変革の波は、先生方の医院継承にも大きな影響を与えています。
2. 2026年度診療報酬改定の主な見通しと注目ポイント
2026年度診療報酬改定は、2024年4月に施行された医師の働き方改革の本格適用、そして団塊ジュニア世代が後期高齢者となり始める2040年を見据えた、極めて重要な改定となります。現時点での情報や厚生労働省の議論から、いくつかの重要な見通しと注目ポイントが挙げられます。
2-1. 2040年を見据えた医療提供体制の再構築
2040年には、75歳以上の後期高齢者の人口がピークを迎え、医療ニーズがさらに増大すると予測されています。この超高齢社会を支えるため、効率的で質の高い医療提供体制の構築が不可欠となります。
- 地域完結型医療の推進
病院完結型から地域完結型医療への移行がさらに加速し、在宅医療や介護施設での医療の役割がより一層重視されるでしょう。 - 医療・介護・福祉のシームレスな連携:
医療機関と介護施設、地域の福祉サービスとの連携を強化するための評価がさらに深掘りされます。多職種連携の促進、情報共有の仕組み作りが重点的に議論されるでしょう。 - 外来機能の明確化と連携
大病院と地域のクリニックの役割分担がさらに明確化され、クリニックの「かかりつけ医機能」への評価が強化される可能性があります。紹介・逆紹介の推進も一層求められます。
重点領域
2-2. 医療DXのさらなる深化とデータヘルスの推進
医療DXは、もはや手段ではなく、医療提供体制の基盤として位置づけられます。単なるデジタル化に留まらず、データを活用した効率的で質の高い医療の実現が目指されます。
- 電子カルテの標準化と普及
現在、医療機関ごとの電子カルテシステムに互換性がないという課題がありますが、2026年度改定では、電子カルテ情報の標準化や相互運用性の確保に向けた具体的な施策、および電子カルテの導入・更新を促すインセンティブが強化される可能性があります。 - 医療情報ネットワークの拡充と活用
マイナンバーカードを活用した医療情報連携基盤のさらなる拡充と、その情報を診療に活かすことへの評価が検討されます。これにより、患者の受診歴や薬剤情報などを、複数の医療機関で共有し、より安全で質の高い医療を提供できる体制が目指されます。 - オンライン診療の適切な評価
オンライン診療の特性を踏まえた上で、対面診療との連携や、情報通信技術を活用した効果的な診療への評価が議論されるでしょう。
具体的な施策
2-3. 医師の働き方改革の定着とタスク・シフト/シェアの推進
2024年4月から施行された医師の労働時間上限規制が本格的に定着する時期として、医療現場の持続可能性を確保するための施策がさらに強化されます。
このチャートからもわかるように、閉院に伴う費用や手間を抑えたい、そして後継者候補が親族以外である場合、第三者継承が最適な選択肢となる可能性が高いと言えます。
- 多職種連携によるタスク・シフト/シェアの評価
医師が行ってきた業務を看護師、薬剤師、医療事務などの他職種が分担することで、医師の負担を軽減し、専門性を活かした医療提供を可能にするための新たな評価体系が導入される可能性があります。 - 医療従事者の処遇改善の継続
医療現場を支える看護師やコメディカルスタッフの確保は喫緊の課題であり、賃上げを含む処遇改善に向けた施策が引き続き検討されるでしょう。これは、クリニックの人件費にも影響を与える可能性があります。
具体的な施策
2-4. 新興感染症への対応能力の強化と平時からの準備
- 感染症対策に係る評価の継続・拡充
感染症対策に継続的に取り組む医療機関への評価や、BCP(事業継続計画)策定へのインセンティブなどが検討される可能性があります。 - 地域における感染症対応体制の構築
地域の中核病院と診療所の連携による、感染症発生時のスムーズな医療提供体制の構築が求められます。
具体的な施策
新型コロナウイルス感染症の経験から得られた教訓を踏まえ、平時から有事に備える医療提供体制の構築が重要視されます。
2-5. 経営効率化と医療の質の維持・向上
医療機関の経営状況は厳しさを増しており、効率的な経営と医療の質の維持・向上の両立が求められます。
- 医療機能に応じた評価の適正化
医療機関の規模や機能に応じた診療報酬の適正化が図られ、効率的な経営を行う医療機関が評価される傾向が強まる可能性があります。 アウトカム評価の導入・拡大: 診療プロセスだけでなく、治療結果(アウトカム)に基づいた評価が導入・拡大されることで、より質の高い医療提供を促す仕組みが検討されるでしょう。
具体的な施策
これらの見通しから、2026年度改定は、医療機関にとって「超高齢社会への対応」「医療DXの活用」「持続可能な働き方改革」がより一層強く求められる改定となると予想されます。これらの動向をいち早く捉え、経営戦略に反映させることが、今後のクリニック経営、ひいては医院継承の成功に直結すると言えるでしょう。
3. 診療報酬改定が医院継承に与える具体的な影響
診療報酬改定は、表面的な点数の増減だけでなく、クリニックの収益構造、運営体制、そして市場価値にまで影響を及ぼします。これは、医院継承を検討する売り手医師にとっても、譲受を考える後継者にとっても、非常に重要な要素となります。
3-1. 譲渡価格への影響
診療報酬改定は、クリニックの「収益性」に直結するため、その譲渡価格に大きな影響を与えます。
- プラス改定の診療科・領域
特定の診療行為や在宅医療、医療DX推進に関連する加算などが新設・拡充された場合、その領域に強みを持つクリニックは収益性が向上し、結果として譲渡価格が高まる可能性があります。後継者にとっても、将来の収益が見込みやすくなるため、魅力的な案件となります。 - マイナス改定・要件厳格化の診療科・領域
一方で、診療点数が引き下げられたり、算定要件が厳格化される診療科や領域では、収益が減少する可能性があります。これにより、クリニックの評価額が下がり、譲渡価格にも影響が出るでしょう。後継者側から見ても、収益の見通しが立ちにくくなるため、敬遠される傾向にあります。 - 設備投資の必要性
医療DX推進などにより、新たなシステム導入や設備投資が必須となる場合、譲渡価格にこれらのコストが上乗せされるか、あるいは譲渡後に後継者が負担することになるため、譲渡価格の交渉に影響を与える可能性があります。
3-2. 後継者の探しやすさ・選びやすさへの影響
診療報酬改定は、後継者がクリニックを選ぶ際の判断基準にも影響を与えます。
- 診療方針との合致
改定により特定の診療分野(例:在宅医療、予防医療)が重視されるようになると、その分野に意欲のある後継者にとっては魅力的な案件となります。先生方のこれまでの診療方針と、国の医療政策の方向性が合致していれば、より後継者が見つかりやすくなるでしょう。 - 経営の安定性への懸念
マイナス改定や厳しい要件変更が続くと、後継者はクリニックの将来的な経営の安定性に不安を感じ、譲渡交渉が難航する可能性があります。特に、経営経験の少ない若手医師にとっては、リスクと感じられる要素が大きくなります。 - 専門性の需要変化
改定によって特定の専門性が高く評価されるようになれば、その専門を持つ医師からの引き合いが増え、後継者の選択肢が広がる可能性があります。
3-3. 継承スキーム・交渉内容への影響
診療報酬改定は、事業譲渡や医療法人出資持分譲渡といった継承スキームの選択や、契約交渉の内容にも影響を及ぼします。
- 事業譲渡の場合
クリニックの資産(土地、建物、医療機器など)と営業権が譲渡対象となります。診療報酬改定によって営業権の評価額が変動する可能性があるため、改定内容を考慮した上で、適切な評価を行う必要があります。 - 医療法人出資持分譲渡の場合
医療法人全体の評価に診療報酬改定が間接的に影響を与えます。法人の収益性が変動することで、出資持分の価値も変動する可能性があります。 - 引継ぎ期間の調整
改定内容への対応や新たなシステムの導入、スタッフの研修などが必要となる場合、後継者が円滑に事業を開始できるよう、引継ぎ期間を通常よりも長く設定するなどの調整が必要になることがあります。
このように、診療報酬改定は医院継承のあらゆる側面に影響を及ぼします。そのため、改定内容を正確に理解し、それを踏まえた上で継承戦略を立てることが極めて重要となります。

4. 2026年度診療報酬改定を見据えた医院継承成功のための戦略
2026年度診療報酬改定の動向を理解した上で、いかにして円滑かつ有利な医院継承を実現するか。ここでは、そのための具体的な戦略を解説します。
4-1. 早期の情報収集と専門家への相談
- 情報収集の徹底
厚生労働省や中医協の公式サイト、医療系ニュースサイトなどで、診療報酬改定に関する最新情報を常にチェックしましょう。特に、中医協の議論の議事録などは、今後の改定の方向性を示唆する重要な情報源となります。 - 専門家への相談の早期化
診療報酬改定は複雑であり、その内容を正確に理解し、自院への影響を予測することは容易ではありません。医院継承の専門家(M&A仲介会社、税理士、弁護士など)は、改定のポイントを熟知しており、先生方のクリニックの状況に合わせて具体的なアドバイスを提供してくれます。
- 「譲渡相談から候補者探索まで1年以上かかることも少なくありません。後継者はすぐに見つかるわけではないため、良い候補者と出会うための時間を確保できるよう、早めの相談をお勧めします。」
- 「急な継承を希望されるケースもありますが、急であればあるほど、良い形での継承が困難なことが多いように見受けられます。」
- 「理想のご勇退を実現するためにも、できる限り早めの判断・行動をおすすめしております。」
4-2. クリニックの「強み」を明確にし、付加価値を高める
診療報酬改定によって、特定の診療分野や医療提供体制が評価される場合、それに合わせてクリニックの「強み」を明確にし、付加価値を高めることが重要です。
- 得意分野の強化
改定で評価される可能性のある診療分野(例:在宅医療、生活習慣病管理、オンライン診療など)がある場合、その分野の専門性をさらに高め、実績を積むことで、後継者にとって魅力的なクリニックとなります。 - 医療DXへの積極的な投資
システムのオンライン化など、医療DXへの積極的な取り組みは、業務効率化だけでなく、後継者からの評価も高めます。 - 地域連携の強化
地域包括ケアシステムの推進に対応するため、地域の医療機関や介護施設、薬局などとの連携を強化し、地域医療における存在感を高めることが、後継者にとっての安心材料となります。
4-3. 譲渡価格の適正な評価と交渉戦略
診療報酬改定の影響を考慮し、適正な譲渡価格を算出することが不可欠です。
- 無料査定の活用
エムスリー医院継承サービスでは、直近の確定申告書や決算書を基に、譲渡価格の簡易査定を無料で行っています。まずは自院の現在の価値を把握することから始めましょう。 - 営業権」の理解
譲渡価格は、土地・建物・設備などの「有形固定資産」に加えて、「営業権」が加算されます。営業権は、現在の収益性や立地、診療科目そして後継者(担い手)の需要によって変動します。診療報酬改定によって、これらの要素がどのように変化するかを把握し、交渉に臨む必要があります。 - 複数の候補者との面談
譲渡価格の交渉を有利に進めるためには、複数の後継者候補と面談し、比較検討することが有効です。エムスリーでは、34万人以上 の医師会員ネットワークを活用し、多くの開業検討医師と出会える可能性を提供しています。
- 「募集開始から1か月で30件もの候補者からの申込」 や、「売主優位の状況を作れたため、希望譲渡価格からの一切値下げ無く契約に至りました」 といった事例もあります。
4-4. 従業員の雇用継続と患者への配慮
円滑な医院継承には、従業員の雇用継続と患者への丁寧な情報提供が不可欠です。
- 従業員の雇用維持
医院継承の場合、原則として全従業員の雇用を継続します。譲渡契約に雇用条件の特約を入れることも一般的であり、スタッフの不安を払拭することで、スムーズな引継ぎに繋がります。 - 患者への丁寧な告知
閉院とは異なり、継承であれば患者さんは引き続き同じ場所で医療を受けられます。継承の旨を患者に丁寧に説明し、理解を得ることで、患者離れを防ぐことができます。
5. エムスリー医院継承サービスが提供する最適なソリューション
診療報酬改定の不確実性が高まる現代において、開業医の先生方が安心して理想のリタイアを実現するためには、信頼できる専門パートナーの存在が不可欠です。エムスリー医院継承サービスは、その課題を解決するための最適なソリューションを提供します。
5-1. エムスリーが選ばれる3つの理由
エムスリー医院継承サービスは、以下の3つの強みにより、多くの先生方から選ばれています。
- 1.国内最大級の医師会員基盤
- エムスリーは、34万人以上の医師会員を有するm3.comを運営しています。この圧倒的なネットワークを活用し、先生方のクリニックに最適な後継者を広範囲から探索します。
- 2万人以上の開業検討医師が開業希望条件を登録しており、最適な候補者に迅速にアプローチできます。
- 毎年2,500件以上の継承希望医師からのお問い合わせがあり、他社では見つからなかった条件でも、適切な後継者を見つけ出すことが可能です。
- 2.一貫したサポート体制
- 譲渡の相談から、後継者探索、候補者との面談、基本合意の締結、最終契約、譲渡実行まで、医院継承の全プロセスを経験豊富なコンサルタントが一貫してサポートします。
- 過去300件超の支援実績に基づくノウハウをもとにエムスリーのコンサルタントが、先生に最適な譲渡スキームを提案し、円滑な継承を実現できるよう尽力します。
- 3.厳重な秘密保持体制
- 先生方の大切な情報が外部に漏洩することのないよう、厳重な秘密保持体制を敷いています。先生の許諾なしに情報を外部に提供することは一切ありませんので、ご安心ください。
- ノンネーム情報(クリニックが特定できない範囲の情報)での情報提供により、秘密を保持しながら広範囲に候補者を募ることが可能です。
5-2. 豊富な成功事例
エムスリー医院継承サービスでは、サービス開始以来300件超の医院譲渡支援を実現してきました。その中には、以下のような多様な成功事例が含まれます。
- 首都圏メジャー科での譲渡成功事例
神奈川県の内科・消化器内科の事例では、募集開始からわずか1ヶ月で約30件の申込があり 、売主優位の状況を作れたため、希望譲渡価格から一切値下げすることなく成約に至りました。 - 短期間(半年以内)での譲渡成功事例
東京都の呼吸器内科の事例では、理事長の急逝という緊急のケースでも、初回相談から約6ヶ月で継承完了まで導いた実績があります。他社では見つからなかった後継者を、わずか2週間で面談に繋げることができました。 - 開業希望者が少ない地域での譲渡成功事例
福島県の皮膚科クリニックの事例では、他社で1年間募集してもトップ面談まで至らなかった案件が 、エムスリーの約32万人のデータベース と隣接県まで範囲を広げた探索により、半年間で4件の申込を獲得し 、無事に譲渡が実現しました。
これらの事例は、エムスリーの強みである医師ネットワークと専門性の高いコンサルティングが、様々な状況下での医院継承を可能にしていることを示しています。
5-3. 閉院ではなく「継承」を強くお勧めする理由
閉院は、経営から解放されるというメリットがある一方で、多額の費用や手間がかかり、従業員の解雇や患者さんの転院など、様々な負担が生じます。
それに対し、医院継承は、閉院時にかかるコスト(解体費用、原状回復費用など)が不要になる だけでなく、譲渡による利益を得てリタイアすることが可能です。エムスリーの試算では、閉院では1,200万円ほどの出費があるのに対し、医院譲渡では1,900万円程の利益を得られる可能性があります(東京・内科の例)。また、従業員の雇用継続 や患者さんの継続的な医療提供 、ひいては地域医療インフラの維持 にも貢献できます。
特に、エムスリーでは、他社と比べて2.5倍の高額な評価額(譲渡価格)を実現した実績もあり、「継承」が経済的に優位な状態でリタイアすることに繋がると強くお勧めしています。
まとめ:理想のセカンドキャリアへ向けて、今、動き出す
診療報酬改定は、医院経営に常に変化をもたらす要因です。しかし、その変化を適切に捉え、早期に戦略を立てることで、先生方の理想のリタイア、そして大切なクリニックの円滑な継承を実現することは十分に可能です。
「いつまで診療を続けたいのか?」「リタイア後の人生で何をしたいのか?」といったご自身の想いを整理し、2026年度診療報酬改定の動向を見据えた上で、最適なリタイアプランを検討する時期が来ています。
エムスリー医院継承サービスは、先生方のクリニックの価値を最大限に引き出し、最適な後継者との出会いをサポートします。まずは、お気軽に無料相談をご利用ください。貴院の「想定譲渡価格」や「譲渡スケジュール」、貴院のエリア・科目での「開業希望者数」を知ることから、理想のセカンドキャリアへの第一歩を踏み出しましょう。
エムスリー医院継承サービスは、先生方の疑問や不安に寄り添い、最適なリタイアプランをご提案いたします。秘密厳守でご相談いただけますので、ご安心ください。