特集記事アーカイブ
 開業支援・コンサル
開業支援・コンサル
2016/07/21 施工段階は細心の注意が必要
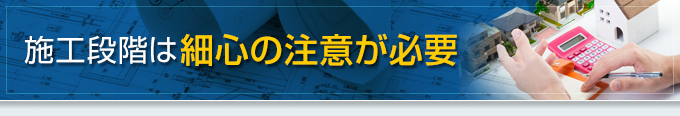
医院を開業する物件が決まると、デザイン・設計・施工のステップに進みます。戸建ての場合は建築段階から、ビルテナント、医療モールなどは契約後に取り掛かることとなります。完成した後でイメージと違ったと後悔しないために、きめ細かな注意が求められるプロセスです。今回はデザイン・設計・施工段階のチェックポイントについてご紹介します。
まず、医院のデザイン・設計・施工は、主に2パターンの発注方法があります。それぞれの特徴は一般的に下記のようなものがあります。いずれの場合も、複数の業者に見積もりを依頼する相見積りをお勧めします。
■ 一括発注
デザイン・設計・施工をすべて同一の業者に一括して発注する方法です。1社にトータルでお願いするため、打ち合わせがまとめて行え先生の手間が少なくて済む点が最大のメリットです。一方で、その業者が特定の分野が得意でないと後から分かっても簡単に変更することはできません。
■ 分割発注(分離発注)
デザイン・設計はA社、施工はB社など、複数の業者に発注する方法です。必要な分野に強みを持つ業者を選らんでクオリティを高めたり、安価で請け負ってくれる業者に依頼することでトータルのコストを抑えることができます。一方で、多くの会社と打ち合わせが必要になり先生のお手間が増えます。
先生が満足されるクリニックの完成には設計士の実力が大きく影響します。医院開業においては、医師の要望を十分に反映し、機能性、デザイン性、経済性の3つをバランスよく設計に生かせる設計士をパートナーとすべきです。具体的には、次のような資質が重要なポイントとなります。
● クリニック設計の経験が豊富にある
● 標榜科目による診療内容の相違をよく理解している
● 医療関連法規や施設基準に精通している
設計・施工を進めていく上で欠かせないのが医師と設計士の間の綿密なコミュニケーションです。先輩開業医や開業支援企業などから、評判のよい設計士を紹介してもらうとよいでしょう。
医院の設計・施工では、細部の変更が全体に影響を及ぼすことがあります。設計士が決まったら、図面をを引く作業の前に、時間をかけて詳細な打ち合わせを行います。下記は代表的な項目ですが、決定すべき事項は多岐にわたります。
● 診療関係
有床・無床、手術を行うか、在宅医療を行うか、リハビリ施設は必要か、院内で行う検査・外注する検査の種類
● 運営関係
院内処方を行うか、点滴ベッドや検査ベッドの数、患者はスリッパに履きかえるのか靴のまま上がるのか、スタッフの人数は何人か
● 設備関係
医療機器は何を導入するか、電子カルテの機種、院内LANのシステム
設計を左右する大きな要因として医療機器があります。たとえばCTやMRIのような大型の機器を入れるか入れないかで、建物の構造が大幅に変わってきます。
大容量の電気を供給するケーブルを引き入れなくてはなりませんし、磁気や放射線の遮蔽工事も必要になります。熱を発生する機器の場合は強力な空調設備が必要となり、内視鏡など洗浄を要する機器には十分な給排水設備も用意しなくてはなりません。
また、大きな機器の場合は、建物が完成してからでは搬入できないこともあります。入口を壊して設置しなければならないことが無いよう、慎重に計画を立てておくことが重要です。
効率のよい医療を行う上で、医療スタッフや患者の動線はきわめて重要です。最短距離で移動ができること、そしてなるべくお互いが交差しないこと、渋滞が生じないことがポイントです。
標榜科によって、問診のあとに検査を行う診療スタイルもあれば、ひと通りの検査を先に行ってから最後に医師が問診を行う診療スタイルもあります。その違いによって患者の動線も、診察室や検査室の配置も変わってきます。先生自身が検査をするのか、スタッフが検査をするのかによっても動線が異なるので、先生が行いたい診療スタイルを設計士に十分に説明し、理解してもらうことが重要です。
追加費用が発生しないかを確認することも重要です。呼吸器科や小児科では、感染症患者さんの隔離用の待合室を検討しなくてはなりません。プライバシー保護のために診察室や検査室では遮音性を高めることや、感染対策のために抗菌床材を使用するなど、医療建築ならではの思わぬ経費が発生します。具体的に細部を詰めていくと必要な経費が積み上がってくるので、優先順位をつけ、実現が可能なもの、不可能なものを選別することになります。
また、デザインの中でも特に難しいのが色使いで、完成後に「自分のイメージしていた色と違う」と不満を持つ先生も多いようです。そのようなことのないよう、なるべく実際に近い形で色調を確認させてもらう手順が必要です。
