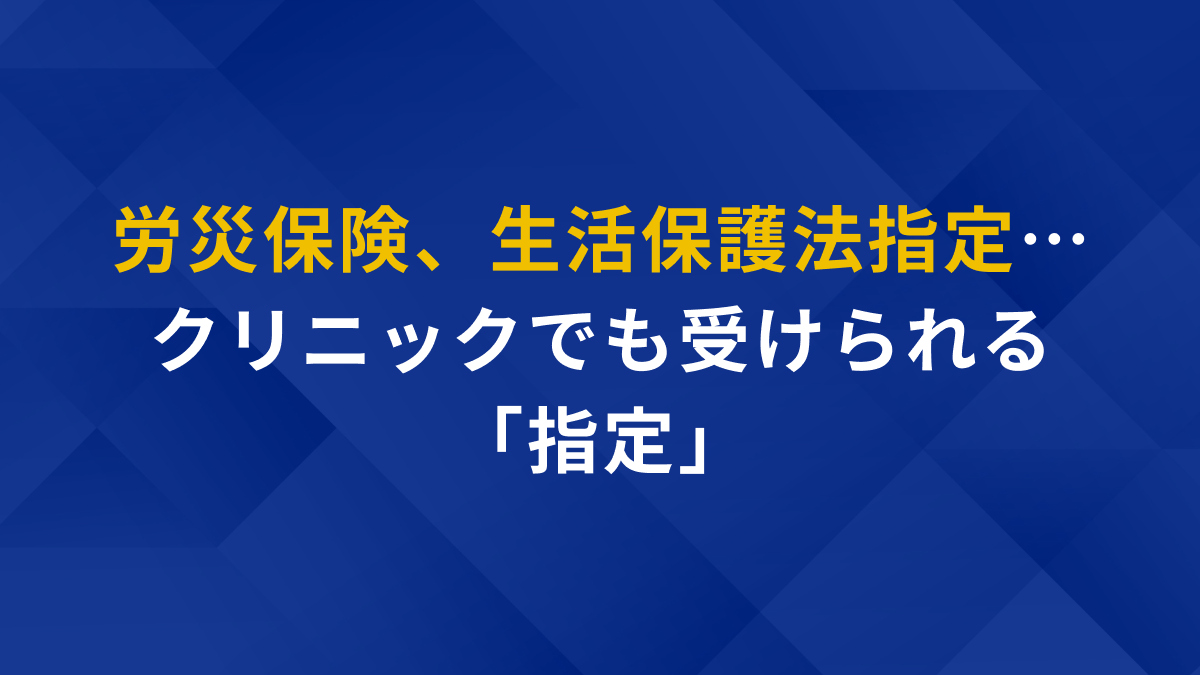
労災保険、生活保護法指定…クリニックでも受けられる「指定」
健康保険法に基づく保険医療機関の指定以外にも、健康保険と別建てまたは併用で医療給付を行う制度が存在します。これらの他にも法律に基づく公費負担制度や自治体の条例に基づく助成制度等が多数存在するため、クリニックの想定する患者層に応じて、必要な指定をあらかじめ受けておくことが求められます。この記事では、一部の指定についてご紹介します。
労災保険指定
労災保険診療は、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険といった公的医療保険とはまったく別の制度です。一般的に、クリニックの収益の中でそれほど大きな存在にはなりませんが、診療科目や立地によっては労災の患者が多く来院する可能性があります。
指定を受けるには、地方厚生局(都道府県事務所)より健康保険法上の保険医療機関としての指定を受けた後、所轄の労働局に申請し、管理者が健保指定と同様の新規指定時講習を受講することが必要です。
労災保険での診療報酬請求は健康保険に準じた点数表で算定し、所轄の労働局へレセプトを提出します。請求は電子請求システムを利用して行い、請求額は1点当たり12円(法人税法の非課税医療機関は11円50銭)となっています。
なお、労災保険指定を受けていない医療機関でも労災診療を行うことは可能です。ただしその場合、医療機関は労災診療点数算定基準で計算した金額の全額を患者から受領します。また、非指定医療機関は政府との間で労災診療に関する契約を交わしていないため、理論的には労災診療点数基準に拘束されませんが、患者に支払われる金額の上限が労災診療点数算定基準によるため、同額で計算するのが通例です。患者から全額受領した後、医療機関は労災診療に関する必要書類を作成・交付し、患者は勤務先を通じて労働局に請求することになります。
生活保護法指定
生活保護法に基づく医療扶助の診療は、福祉事務所長に対し保護を申請し、医療扶助の決定を受けた患者に対して都道府県知事または政令市の市長が指定した医療機関が行わなければなりません。
医療扶助には、患者のもともと加入していた医療保険種別や収入等により、医療扶助として全額給付を受ける「生保単独」の場合と、医療保険による一部負担金を医療扶助から給付する「医療保険併用」があり、それぞれ自己負担の有無等の区分があります。
指定医療機関は、患者が福祉事務所から交付を受けて受診時に持参した「医療券」に基づいて診療を行い、診療の翌月に都道府県の支払基金に請求書を提出してその翌月に支払いを受けることになります。医療機関が生活保護法指定を受けるには所轄の福祉事務所に申請書を提出し、診療所の入口または見やすいところに「生活保護法指定医療機関」である旨を表示しなければなりません。
指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療/精神通院医療)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく自立支援医療は、自立支援医療の種別ごとに都道府県知事または政令市の市長が指定した医療機関が、各療養担当規程に基づき行うものです。指定医療機関として診療を行った医療機関は、翌月のレセプトで患者それぞれの医療保険と併用として支払基金等に提出し、患者自己負担部分については公費より支払いを受けることになっています。