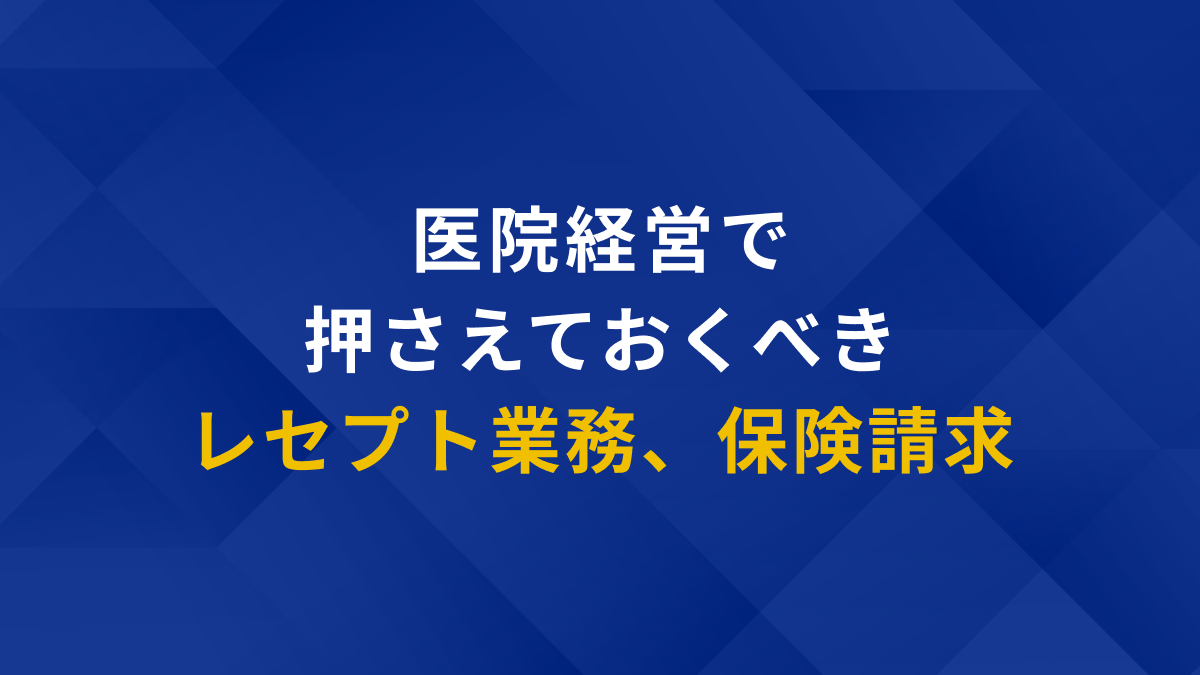
医院経営で押さえておくべきレセプト業務、保険請求の基本
医療機関では医療法に基づく立入検査に加え、保険医療機関として健康保険法に基づく地方厚生局の指導・監査を受けることが必要です。この監査は保険診療と請求に関する適切性を確認するために行われます。以下ではそのことを踏まえて、診療・レセプトの作成・請求・振り込みに関する基礎知識や注意点を解説します。
診療
保険医療機関の認定を受けたクリニックでは、健康保険が適用される診療について、患者から自己負担分を徴収し、残額を保険者に請求することが可能です。保険請求の基本要件として、まず保険医が保険医療機関において診療を行うことが求められます。さらに、健康保険法、医師法、医療法、医薬品医療機器法等の各種関連法令の規定を遵守することが不可欠です。また、保険医療機関及び保険医療養担当規則の規定に従い、医学的に妥当適切な診療を行わなければなりません。そして、診療報酬点数表に定められた通りに請求を行う必要があります。これらの要件を満たさないものは自費診療として別個に行わなければなりません。
自費診療を行う場合は注意が必要です。同一患者の同一疾患に対して保険診療との混合診療は認められていません。保険診療では来院患者に対して適切な傷病名をつけ、必要な検査や投薬、処置などをすべて診療録に記載することが不可欠です。これらの診療行為は電子カルテまたはレセプトコンピューターに入力し、患者の負担割合に応じた一部負担金を窓口で徴収することとなります。一部負担金は療養担当規則第2条の4の2、第5条第1項により規定額の徴収が義務付けられており、任意の減免は認められていません。
レセプトの作成
毎月の保険診療分は患者ごと、保険者ごとに集計し、翌月10日までに診療報酬請求明細書(レセプト)にまとめる必要があります。
レセプト作成時には保険資格の確認が最も重要です。審査支払機関から医療機関へレセプトが返送される「返戻」の中で最も多いのが「保険資格なし」のケースです。これは診療報酬の支払いが保留となるだけでなく、再請求のための事務作業も発生するため、事前の資格確認は特に慎重に行う必要があります。電子カルテを導入する際も、レセプトチェック機能があるものを選んでおくと安心かもしれません。
加えて、通常よりも多くの処置を要した場合や、通常と異なる検査をした場合には、医学的な必要性を説明する症状詳記の添付が求められるため、当該する際にはその記載も必要です。
請求
診療報酬の請求は電子媒体での提出が原則です。健康保険は各都道府県の社会保険診療報酬支払基金(社保または支払基金)へ、国民健康保険および後期高齢者医療保険は各都道府県の国民健康保険団体連合会へ、診療報酬請求書とその明細書を提出することになっています。請求はオンライン電送またはCD-ROM(一部はフロッピーディスク)の郵送もしくは持込みで行います。
振込み
請求を受けた支払基金および国保連(審査支払機関)は、提出されたレセプトを審査し、請求翌月の20日から25日頃に医療機関が届け出た口座に診療報酬を振り込みます。請求内容に問題があると判断された場合は、その部分の支払いを保留してレセプトを返却(返戻)、または該当部分を差し引いた額での振込(査定)となることがあります。
さらに、審査支払機関の審査を通過して振込みを受けた診療報酬であっても、後日、保険者での審査により不適当と判断され、返戻または査定を受けることもあるでしょう。電子請求の義務化以降、患者ごとに薬局の調剤レセプトとの突き合わせ(突合)や、同一患者の複数月分のレセプトを通算して審査する(縦覧)が可能となりました。そのため、支払完了後に保険者から査定を受けるケースが増加傾向にあるようです。
個人開設のクリニックの場合、社会保険診療報酬から源泉所得税が控除された状態で振り込まれることには注意が必要です。月次のキャッシュフロー管理に影響を与えるため、この点を見落とさないように注意しましょう。