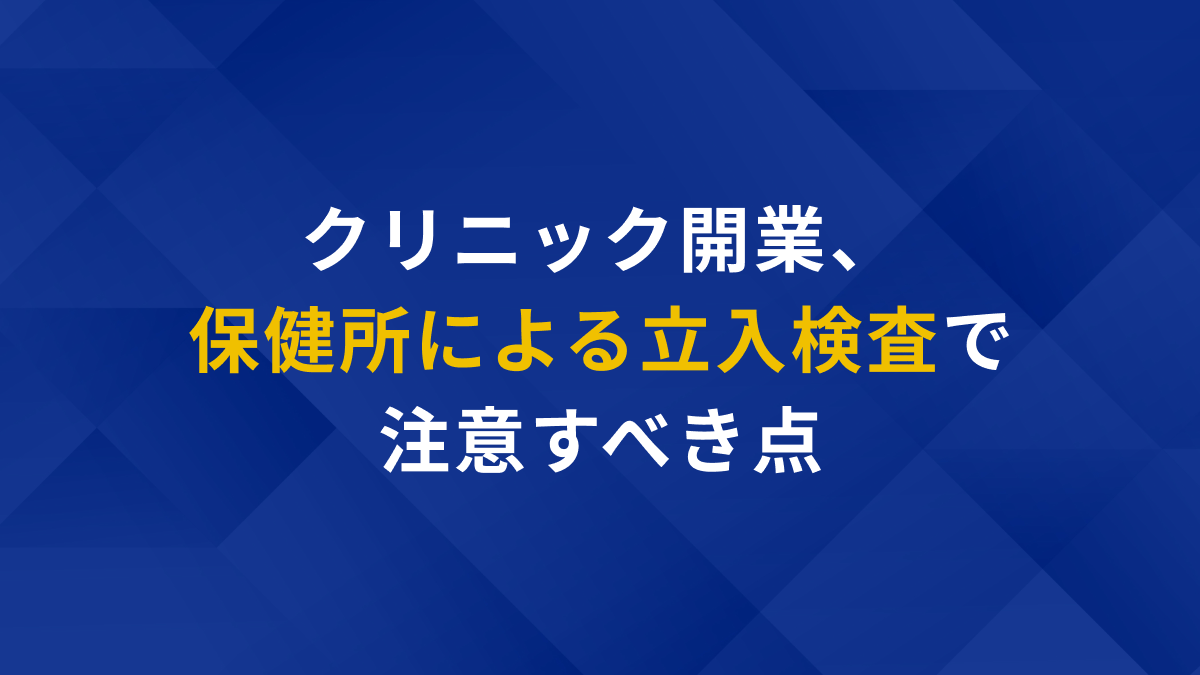
クリニック開業、保健所による立入検査で注意すべき点
医療機関の開設・運営において、保健所による立入検査は避けて通れません。保健所の検査は医療の質と安全性を担保するために行われるものであり、クリニックには適切な準備と対応が求められます。
クリニック開業、保健所による立入検査で注意すべき点
保健所立入検査の目的
保健所による立入検査は、医療機関が適切な医療を提供できる体制を整えているかを確認するために行われます。より具体的には、人員配置や施設・設備の基準への適合性、医療安全管理体制の確認などが主な目的です。開業時の検査では特に、診療環境の安全性や衛生管理体制の確認に重点が置かれます。
注意すべき点として、保健所の立入検査と地方厚生局による保険診療の指導・監査は、まったく性格の異なるものです。保健所の立入検査は医療法に基づく医療機関としての適格性の確認であり、保険診療の適切性を確認する厚生局の監査とは目的が異なります。この違いを理解せずに準備をしてしまうと、必要な対応を見落とす可能性があるでしょう。
立ち入りに法的な根拠はあるのか
医療機関への立入検査には明確な法的根拠があります。医療法第24条では都道府県知事および保健所設置市区の長による監督権が規定され、第25条では立入検査権が定められています。
実際の検査は、医療監視員として指名された保健所職員が実施しますが、医療監視員は医療法第26条に基づき指名された公務員です。医療規則第41条で「医療に関する法規および医療機関の管理について相当の知識を有する者」と要件が定められているため、専門的知識を持つ職員による適切な検査が担保されています。
立入検査の実務としては、通常1~2名の担当者が来院し、約30分程度で院内を確認することが多いです。多くの保健所では、開設届出時または事前相談時に実査の日程を調整します。指摘事項は基本的に口頭で伝えられますが、改善が必要な項目が多い場合は文書での通知と改善報告の提出を求められることもあります。
重要な点として、検査時の状況や指摘事項は医療機関ごとの台帳に記録され、その記録は医療機関の廃止まで継続して保管されます。そのため、初回の立入検査での対応は、その後の運営にも影響を与える可能性があります。改善指導を受けた事項については、確実に対応することが望ましいです。一度指摘を受けた事項は、次回以降の検査でも重点的に確認される傾向にあります。
保健所はどこまで介入できるのか
保健所の医療機関への介入権限は、法律によって明確に規定されています。医療監視員には、医療施設の人員配置から構造設備、診療録、帳簿書類に至るまで、幅広い検査権限が与えられています。特に衛生管理や安全性に問題がある場合は、施設の使用制限や改築命令といった強制力のある措置を講じる権限も持っています。
ただし、無床診療所に関する法規制は比較的緩やかです。医療法第19条では「清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない」と定めているのみで、具体的な基準は各自治体の立入検査要綱などによる行政指導として運用されることが一般的です。
▼無床診療所の構造設備基準(一部)
| 設備区分 | 必要な対策・設備要件 |
| 基本設備 (電気・照明・空調関連) |
|
| 消火設備 |
|
| 防災設備 |
|
| 放射線診療設備 |
|
保健所の監督範囲は施設の物理的構造にとどまりません。診療録の記載・保管方法、医療廃棄物の処理体制、医療従事者の資格確認、医療安全管理体制など、医療機関の運営全般に及びます。一方で、保険診療に関する事項については、原則として介入対象外となっています。
検査頻度については、有床診療所や病院では毎年1回、地方厚生局都道府県事務所との合同で実施されるのが通例です。この際は診療報酬の算定要件に関する確認も同時に行われます。これに対し、無床診療所では開設時の1回を除き、その後は自治体によって5~6年おきとされていたり、数十年間実施されないこともあります。ただし、患者からの苦情や内部告発があった場合には、臨時の立入検査が実施される可能性があります。
このように、保健所の介入範囲と権限は法的に明確に定められていますが、実際の運用では地域による違いが大きいのが特徴です。そのため、開業時に地域の保健所の運用方針を確認し、適切に対応できる体制を整えておくことが重要です。特に開設時の立入検査では、その後の運営にも影響を与える可能性があるため、入念な準備が求められます。
【項目別】実査時のポイント
無床診療所への立入検査では、構造設備面のみならず、管理運営面からも綿密な指導が行われます。以下、主な注意点について解説します。
医療安全体制
医療法施行規則に基づき、管理者による医療安全確保のための包括的な対応が求められています。医療安全管理指針、院内感染対策指針および業務マニュアル、医薬品安全使用手順書、医療機器保守点検計画の整備が必要となります。加えて、医療安全、院内感染対策、医薬品・医療機器の安全使用に関する職員研修の定期的な実施と記録保管も欠かせません。無床診療所においては、院外研修の受講記録による代替も認められています。
実査日程決定後の対応として、管理者に加えて看護師や事務職員の同席が推奨されます。指摘事項の詳細な記録と、即座に改善可能な項目への迅速な対応により、保健所の台帳に課題を残さない運営を心がけましょう。
個人情報保護体制
管理指針の策定と院内掲示等による周知、そして適切な運用が求められます。個人情報の範囲に関して、診療情報だけでなく個人を特定できるあらゆる情報が含まれる点に留意が必要です。
X線照射記録、被ばく管理体制
X線装置保有施設では、装置ごとの照射記録の保管が必須です。加えて、医師または診療放射線技師についてフィルムバッジ等による従事者ごとの被ばく管理が求められ、医療従事者の安全確保において欠かせない要素となっています。
職員の健康管理体制
労働安全衛生法に基づく職員の定期的な健康診断の実施とその記録保管が求められます。職員の健康管理を通じて、安全な医療提供体制を構築することが狙いです。
医薬品保管・管理体制
医薬品の規制区分に応じた厳格な管理基準が設けられており、特に慎重な対応が求められます。麻薬については固定された専用金庫での保管と専用帳簿による在庫管理を行い、向精神薬では施錠可能な設備での保管を原則とし、無人時の確実な施錠が欠かせません。毒薬・劇薬については他の医薬品と区別した保管を行い、毒薬では確実な施錠管理が必要です。さらに、冷所保存品については温度計を備えた専用冷蔵庫での保管が推奨されています。
院内掲示
医療法に基づき、管理者氏名、従事する医師の氏名、診療日および診療時間を院内の見やすい場所に掲示しなければなりません。実査の際に最初に確認される重要項目として位置づけられており、医療機関としての適切な情報公開の姿勢を示しているかが確認されます。
広告内容
マーケティングの章で解説したとおり、医療機関の広告については医療法第6条の5および医療広告ガイドラインで定められた範囲内でのみ掲載が認められていますが、法令・ガイドラインに違反した広告が無いかが確認されます。
消火器またはスプリンクラーの設置
スプリンクラー未設置の建物では、院内の見やすい場所への適正数の消火器設置が必須となります。患者さんと職員の安全確保に向けた基本的な防災対策として欠かせない要件となります。
諸届書類の控え
診療所開設届、X線装置備付届、各種年次報告等の書類の控えについて、変更時や次年度の届出の前提となる重要な記録として、常に時系列での整理・保管が求められます。将来の手続きをスムーズに進めるためにも、適切な管理体制の構築が不可欠です。
診療録、検査記録、処方箋の控え等
医療記録には外部流出を防ぐ体制での保存が求められ、特にカルテについては最後の診療日から5年間の保存が義務付けられています。電子カルテを使用する場合、無断での書き換えができない「真正性」、必要時に速やかに出力・表示できる「見読性」、保存期間中の確実なデータ保持を示す「保存性」という3つの要件が必須となります。
従事者の免許証の確認およびコピーの保管
管理者による医師、看護師等の免許証原本確認は必須であるほか、その写しの院内保管が求められることも。医療従事者の資格管理における基本的かつ重要な業務として認識されています。
X線量測定記録
X線装置における6カ月ごとの漏洩測定と記録保管により、患者と医療従事者双方の安全確保を担保します。定期的な測定・記録を通じて、適切な放射線管理体制を維持していく必要があります。