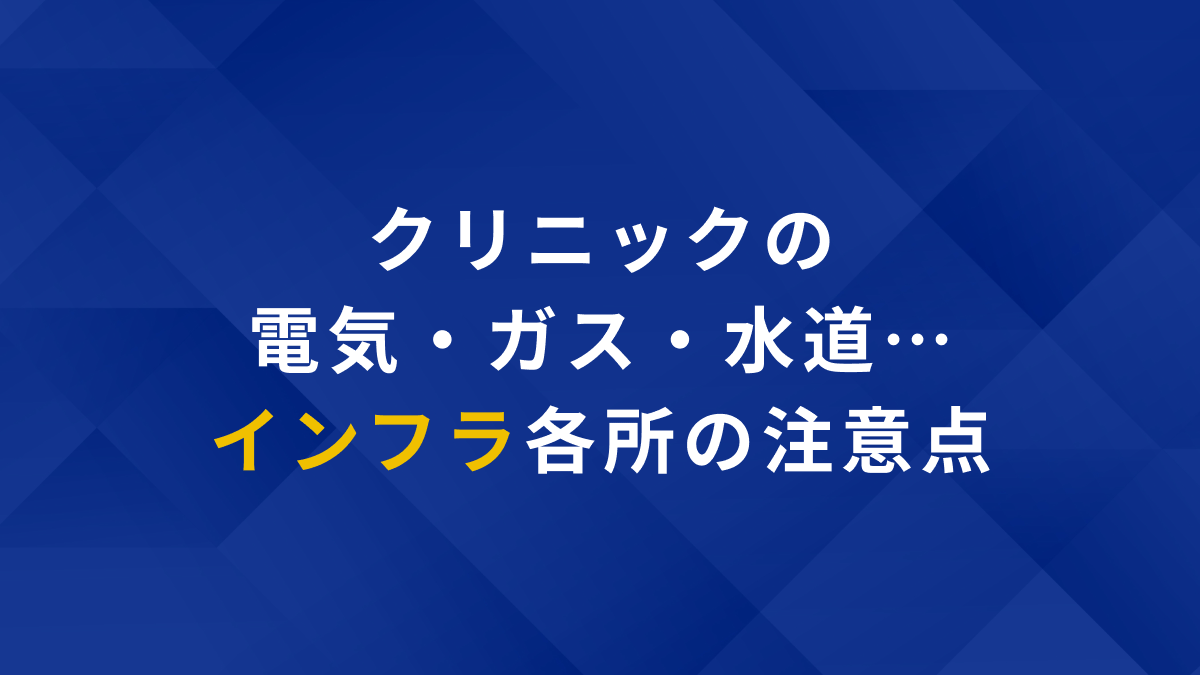
クリニックの電気・ガス・水道…インフラ各所の注意点
医療施設のインフラ設備は、安全で効率的な診療を支える上で重要な役目を果たします。電気、水道、ガスといった設備は、一般的な建物とは異なる医療特有の要件を満たす必要があり、その計画と管理には専門的な知識が求められます。
本章では、クリニック開設時に考慮すべきインフラ設備の要件と管理方法について、法令への適合性や実務的な観点から詳しく解説します。
電気設備
電気容量
医療施設における電源システムは、一般用途の電灯電源(単相100V/200V)と医療機器専用の動力電源(三相200V)の2種類に大別されます。電気の引込方法としては、電柱から建物へ直接引き込む低圧引込み(100V、200V)と、キュービクル(受変電設備)を設置して自施設で電圧を降圧する高圧引込み(6,600V)があります。
キュービクルの設置は初期投資とメンテナンスコストが発生するため、可能であれば回避したい設備です。しかし、電灯電源、動力電源それぞれの容量が50kW以上となる場合は、法令上の要件としてキュービルの設置が必須となります。大規模クリニックやCT・X線装置など大容量機器を複数導入する場合は、必然的にキュービクル設置が必要になりますが、それ以外の場合は慎重な容量検討が求められます。
建物全体の電気容量算出には、入念な事前調査と計画が必要です。導入予定の全医療機器の電気容量と電源種類を確認し、エアコンや照明器具など建築設備の容量も含めて検討します。さらに将来的な機器導入計画も考慮に入れ、各機器のカタログ値に基づいて容量を集計します。実際の使用パターンに基づく同時使用率を考慮し、総合的な容量計算を行います。
特にX線装置やCT装置は、機種により必要電源や容量が大きく異なるため、機器選定段階から電気容量との整合性を検討する必要があります。低圧引込みでX線装置を設置する場合は、配電系統への影響を考慮して事前に電力会社との協議が必須となります。
なお、電気容量については個別具体的な内容になってくることもあって、内装事業者に導入医療機器を伝えたうえで早めに現地確認を依頼しておくことが大切です。大きなトラブルを避けるためには何より、「クリニック開業に強い(クリニック施工経験豊富な)内装事業者や弱電業者に依頼することが重要と言えます。
コンセント
電気回路の設計は、診療の安定性と医療安全に直結する重要な事項です。不適切な回路設計は、診療中のブレーカー遮断や医療機器の誤作動を引き起こす可能性があるため、特に慎重な計画が必要です。
オートクレーブなどの大容量機器、画像診断装置、物理療法機器、レーザー治療装置などの電源容量の大きな機器については、専用回路を確保し、他の機器との干渉を防止する必要があります。また、超音波診断装置、心電計、生体モニター、内視鏡システムなど、電流・電圧変動の影響を受けやすい機器については、安定した電源供給が可能な回路構成が求められます。
各診療室の回路は原則として独立させ、他室の機器使用状況に影響されない設計とすることが重要です。特に整形外科のリハビリ室など、複数の物理療法機器を使用する場所では、機器配置計画と電源容量を綿密に検討する必要があります。
コンセントの設置位置については、床からの高さを原則30cmとしながらも、頻繁な使用が想定される箇所では作業負担軽減のため50~60cmとすることが推奨されます。全てのコンセントはアース付とし、診察デスクや受付周りでは十分な数のコンセントを確保します。医療機器使用場所では、各機器の容量に応じた専用コンセントを適切に配置することが必要です。
LAN配線
現代の医療施設において、情報通信ネットワークは診療業務の基盤となる重要なインフラです。電子カルテシステムでは、診療情報管理、オーダリング、処方管理、予約システムなどの機能が統合されており、安定した通信環境が必要です。医療画像系統では、放射線画像、内視鏡画像、超音波画像などの大容量データを扱うPACSシステムの運用が必要です。さらに一般的な事務作業用として、インターネット接続環境も必要となります。
これらのシステムは、セキュリティ確保のため物理的に分離することが推奨されます。将来的なシステム拡張や機器増設に備え、余裕を持った配線設計が必要です。回線については、高速で安定した通信が可能な光回線の導入が推奨され、バックアップとしてADSLやモバイル回線の併用も検討に値します。
セキュリティ対策として、ファイアウォールの設置やネットワークの分離、アクセス制御の実装、ログ管理システムの導入などが必要です。これらの対策は、患者情報の保護のために不可欠な要素となります。
照明器具
医療施設における照明器具は、診療の質と快適性に直接影響を与えます。手先などをしっかりと視認できるよう、診察室や処置室では500~700lxという十分な照度が必要です。特に注射や採血などの精密な作業を行う場所では、より明るい照度設定が求められます。
照明器具のレイアウトは、患者と医師の位置関係、スタッフの作業位置を十分に考慮して決定する必要があります。診察時に患者の顔に影ができたり、処置時にスタッフの手元が暗くなったりすることを防ぐため、光源の位置と方向性を慎重に検討します。スイッチの配置も重要で、一般的な建築物のように入口付近だけでなく、職員の作業動線に沿った位置に設置することで、業務効率の向上につながります。
眼科の診察室など、頻繁に照明の明暗調節が必要な場所にはフットスイッチの設置が有効です。エコー検査室や内視鏡検査室などでは、検査時の視認性向上のため調光機能付きの照明を採用します。また、受付での一括制御を可能にするため、各部屋のスイッチと連動した3路スイッチの設置も検討に値します。
点滴室など、患者が長時間過ごす場所では、照明の眩しさによる不快感を防ぐための工夫が必要です。照明の区分けや間接照明の活用により、快適な療養環境を整えることができます。こうした細かな配慮が、患者満足度の向上にもつながります。
院内放送
院内放送設備は、単なる音楽再生ではなく、診療環境の質を向上させる設備にもなりえます。ただ、近年では、コストダウンの観点から院内放送を導入しないクリニックが増えてきており、そのあたりは方針と兼ね合いになってきます。
呼び出し放送システムについては、BGMとの兼用か別系統かを検討する必要があります。兼用する場合は、呼び出し時にBGMの音量を自動的に下げる機能や、一時的に停止する機能を持つ機種を選定します。操作性の観点からは、別系統のシステムの方がシンプルで使いやすい利点があります。
マイクの選定は特に重要です。誤操作による患者情報の漏洩を防ぐため、スイッチの状態が明確に分かる機種を選ぶ必要があります。例えば、マイクのスイッチが入りっぱなしになり、診察内容が待合室に流れてしまうといったトラブルを防止する必要があります。
スピーカーの設置は、待合室だけでなく、診察室やトイレにも検討する価値があります。診察室のスピーカーは患者とのコミュニケーションを円滑にし、トイレのスピーカーは排泄音などのマスキング効果を発揮します。各部屋のスピーカーには個別の音量調節機能を設け、それぞれの空間に適した音量設定を可能にすることが推奨されます。
空調設備
医療施設の空調システムは、個別方式が推奨されます。これは、各部屋の用途や使用状況に応じて細かな温度管理が可能となるためです。個別方式には電気式とガス式があり、それぞれに特徴があります。電気式は初期投資が比較的安価ですが、ランニングコストはガス式の方が有利です。最新のガス式システムには停電時に自家発電として利用可能な機種も登場しています。
空調機器の選定では、一般的な1対1タイプ(室内機と室外機が1対1で対応)とマルチタイプ(1台の室外機で複数の室内機を制御)のどちらを採用するかを検討します。設置スペースが限られている場合はマルチタイプが有利ですが、室内機の個別運転や温度調節の可否を確認する必要があります。特にMRI室やCT室など、精密機器の安定稼働のために厳密な温度管理が必要な部屋では、個別制御が可能な機種を選定することが絶対条件となります。
空調システムの選定は、建物全体の電気容量設計とも密接に関連します。電気式を採用する場合、全体の電気容量が50kWを超えないよう注意深く検討する必要があります。また、将来の機器増設なども考慮に入れた余裕のある設計が望ましいでしょう。
換気方式
医療施設における換気設計は、感染対策と快適性の両立を図る上で重要です。換気方式には、自然換気と機械換気があり、機械換気はさらに第一種、第二種、第三種の3つに分類されます。
- 第一種換気:給気と排気の両方にファンを使用
- 第二種換気:給気のみファンを使用
- 第三種換気:排気のみファンを使用
診察室や待合室には第一種換気を採用し、室内の空気が効率的に入れ替わるよう、給気口と換気扇の位置を適切に配置します。特に注意が必要なのは、給気口の位置と患者の着座位置の関係です。冬季に冷たい外気が直接患者に当たることのないよう、十分な配慮が必要です。また、診察室の換気扇の位置は、診察時の会話に支障をきたさないよう、騒音にも配慮が必要です。
感染対策の観点から、診察室は給気量を控えめに設定し、室内の空気が待合室などに流れ出にくい設計とすることも推奨されます。感染症対策が特に必要な隔離室では第三種換気を採用し、室内を陰圧に保つことで、汚染空気の拡散を防止します。同様の考え方で、トイレや洗浄室など臭気や湿気の発生する場所も陰圧設計とします。
手術室の換気は特に重要で、清浄な環境を維持するため室内を陽圧に保ちます。給気にはHEPAフィルターを使用し、清浄な空気を供給します。排気は前室を経由する二段階方式を採用し、汚染の拡散を防止します。また、熱交換換気の採用は、一般住宅では省エネ効果が期待できますが、医療施設では人の出入りが多く、その効果は限定的であることを理解しておく必要があります。
自家発電設備
東日本大震災時の大規模停電とその後の計画停電の経験から、医療施設における非常用電源の重要性が再認識されています。この教訓を踏まえ、自家発電設備の導入を検討するクリニックが増加傾向にあります。
しかし、自家発電設備の導入には重要な留意点があります。一般に想像されるような「建物全体の通常運用の維持」は現実的ではありません。実際の運用では、照明器具、人工呼吸器、保育器など、生命維持に直結する機器への最低限の電源供給が主な役割となります。さらに、自家発電設備からの電源は電圧が不安定になる可能性があるため、精密医療機器の使用は推奨されません。
設備導入には多額の費用が必要となり、さらに維持管理にも相当のコストが発生します。自家発電設備の動力源はエンジンであるため、自動車と同様に定期的なメンテナンスが必須です。また、部品の定期交換も必要となることから、イニシャルコストだけでなく、継続的なランニングコストも考慮に入れる必要があります。
導入を検討する際は、最低限必要な電気容量の精査、供給対象の優先順位付け、設置スペースの確保など、総合的な計画立案が重要です。これらの要素を慎重に検討することで、効果的な非常用電源システムの構築が可能となります。
太陽光発電設備
太陽光発電は、東日本大震災以降、地球温暖化対策や原子力発電所の問題を背景に、再生可能エネルギーとして注目を集めています。電力会社による固定価格買取制度の開始も、普及を後押ししている要因です。太陽光発電設備を設置すると、晴天時には自施設での電力供給が可能となり、電気料金の大幅な削減が期待できます。さらに、余剰電力は電力会社による買取りの対象となるため、経済的なメリットも見込めます。
しかし、太陽光発電設備を自家発電設備の代替として考えることは適切ではありません。その理由として、太陽光発電システムの運用には外部からの電力供給が必要となる点が挙げられます。停電時には、わずか1回路分のコンセントしか使用できず、通常時のような発電量は期待できません。
さらに重要な制約として、発電した電力を大量に蓄電することができない点があります。そのため、曇天や雨天時には十分な発電量が得られず、安定した電力供給は望めません。夜間も当然ながら発電はできません。
これらの特性から、太陽光発電設備は省エネルギーやランニングコスト削減の観点では有効な選択肢となりますが、非常用電源としては機能しないことを十分に理解する必要があります。医療施設における非常時の電源確保という観点では、自家発電設備とは明確に区別して検討すべき設備といえます。
水道設備(排水設備・給水設備)
医療施設における排水設備は、開業に不可欠なインフラです。空調や電気設備は運用方法の工夫である程度の妥協が可能ですが、手洗いや流し台は保険診療を行う上でも重要なインフラであり、適切な排水設備なしには医療機関の運営そのものが成立しません。
給水設備と排水設備は、その基本原理が大きく異なります。給水設備は圧力によって水を供給するため、方向や高低差に関係なく配管が可能です。一方、排水設備は重力を利用した自然流下方式を採用しているため、必ず高所から低所への傾斜が必要となります。この物理的制約が、医療施設の設計に大きな影響を与えます。
特に医療施設では、バリアフリー対応が重要な要件となります。一般的な商業施設では床の段差が許容される場合でも、医療施設では患者の安全性と利便性を考慮し、可能な限り段差を排除する必要があります。この要求に対応するため、医療モールなどでは共用部廊下より区画内の床を250~300mm程度低く設定し、排水管の傾斜確保と床面のバリアフリー化を両立させる工夫が施されています。
物件選定時の注意点・ポイント
物件選定時の重要な確認事項として、区画内の排水設備の有無と位置を精査する必要があります。スケルトン物件では排水管の立ち上がりが視認できますが、事務所仕様の物件では既存のトイレや流し台の位置から排水設備の配置を把握する必要があります。
区画内に排水設備がない場合、新設工事が必要となりますが、これには建物の構造的な制約と建物オーナーの承諾が必要です。特に既存建物では、排水管の新設が物理的に困難な場合も少なくありません。このような専門的判断が必要なケースでは、設備設計の専門家による事前調査が不可欠です。
新築物件や地下ピットを有する建物では、比較的自由な排水設備の配置が可能です。ただし、新築の場合は早期のプラン確定が求められ、工事スケジュールに大きく影響する点に注意が必要です。
その他の排水設備
空調設備の排水も重要な検討事項です。業務用空調機器からの排水量は家庭用に比べて格段に多く、適切な排水処理が必要となります。最新の天井埋込型空調機にはドレーンアップ機能(排水ポンプ機能)が搭載されており、排水管の勾配確保が比較的容易になっています。ただし、天井裏の空間確保など、建築的な制約との調整が必要です。
手洗い設備においても、ドレーンアップ機能を持つ製品が登場し、設置場所の自由度が増しています。一方、トイレの排水に関しては、同様の機能を持つ製品もありますが、医療施設という特性を考慮すると、機械的なトラブルリスクを避けるため、自然流下方式を採用することが推奨されます。
このように、給排水設備の計画には建築、設備、医療機器など多岐にわたる専門知識が必要となります。また、新技術の採用可否判断や構造的な制約の確認など、総合的な検討が求められます。そのため、物件選定から設計段階において、関連分野の専門家を交えた慎重な検討プロセスが不可欠となります。将来的な拡張性や設備更新の可能性も考慮に入れ、長期的な視点での計画立案が重要です。
医療用ガス設備
医療用ガス設備は、患者の生命維持に直結する重要なライフラインです。主として酸素、圧縮空気、亜酸化窒素(笑気ガス)、二酸化炭素などの供給を担い、その安全管理は医療施設運営の根幹を成します。
理想的には、臨床工学技士や専門技術者による管理体制が望ましいものの、個人クリニックの実態としては、院長自身が管理責任者となるケースが多く見られます。そのため、院長は医療用ガス設備に関する基礎知識を備え、必要に応じて専門業者との連携体制を構築することが求められます。適切な供給体制の確保と安全性の担保には、管理者の十分な知識と、専門家による定期的なサポートが不可欠です。
医療ガス安全管理委員会の役割
医療ガス安全管理委員会は、患者の生命維持に必要不可欠な医療用ガスの安全管理を目的とした組織体です。病院および入院施設を持つクリニックには、その設置が法令で義務付けられています。委員会の構成は、医師、薬剤師、看護師、臨床工学技士、設備管理スタッフなど、多職種による横断的な体制が基本となります。特に麻酔科医が常勤する施設では、その参画が必須要件となります。
委員会の具体的な責務には以下が含まれます。
- 医療用ガス設備の定期点検の実施と監督
- 設備工事の安全管理と監督
- 点検記録の適切な管理と保管
- 医療スタッフへの安全管理研修の企画・実施
医療ガス安全管理委員会は年1回以上の開催が求められ、必要に応じて専門業者の参加も要請されます。一方、無床クリニックは委員会設置の法的義務は課されていませんが、院長または相応の知識・技術を有する者による適切な安全管理体制の構築が必要とされています。
関連法規
医療用ガスの取り扱いに関しては、複数の法規制が存在し、それらの理解と遵守が不可欠です。特に重要な法規として、「高圧ガス保安法」と「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」が挙げられます。
高圧ガス保安法は、医療用ガスを含む高圧ガス全般の製造、貯蔵、販売に関する安全基準を規定しています。同法では、高圧ガス設備の技術基準や保安管理体制の要件、定期点検の実施基準、さらには事故防止対策の具体的措置について詳細な規定を設けています。
一方、薬機法では医療用ガスを医薬品として位置づけ、その品質管理と安全性確保に関する詳細な規定を定めています。品質管理基準や保管・管理方法、使用期限の管理、安全性確認の手順など、医薬品としての厳格な管理要件が示されています。
これら法規制の要件を満たすため、医療施設は適切な管理体制の構築と、定期的な見直しを行う必要があります。ガスの種類や使用量に応じた適切な保管設備の整備、定期的な点検と記録の保管、スタッフへの教育訓練の実施など、包括的な安全管理体制の確立が求められます。このような体制整備は、患者の安全確保だけでなく、医療施設のリスクマネジメントの観点からも極めて重要な要素となります。