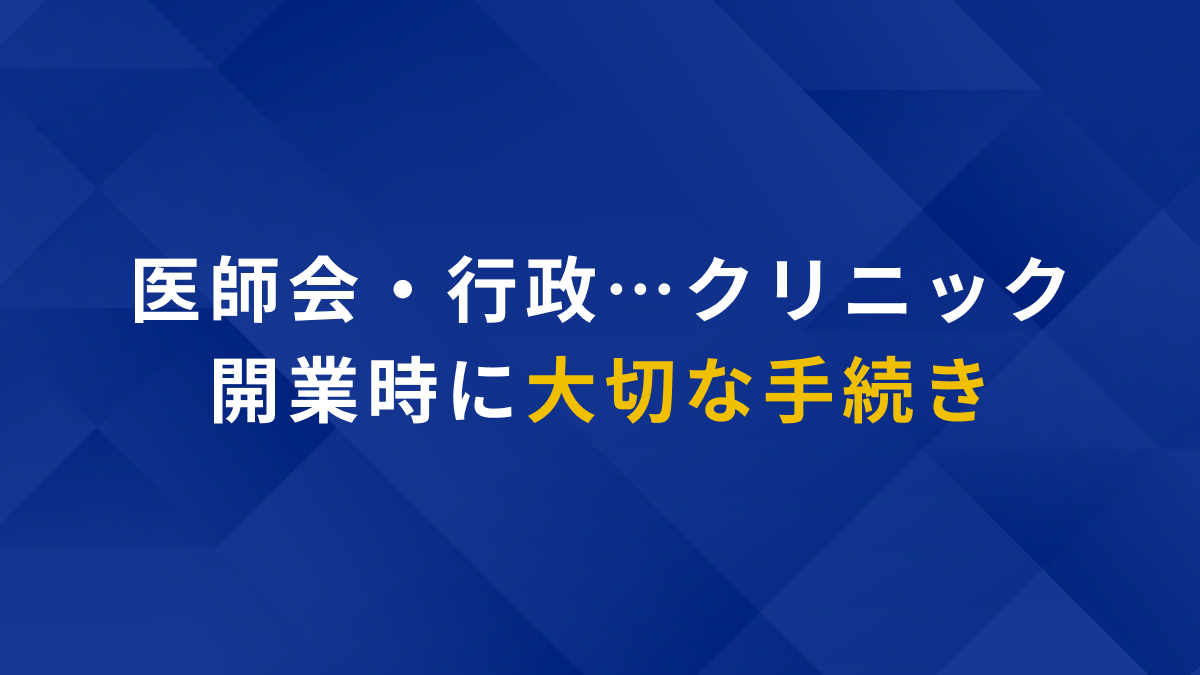
医師会・行政…クリニック開業時に大切な手続き
クリニック開設時には法的な手続きが必要
医療機関の開設には、医療法や健康保険法に基づく複数の法的手続きが必要です。これらの手続きを適切に行うことで、開業後のスムーズな運営が可能となります。各手続きには定められた期限や要件があるため、慎重な対応が求められます。
基礎知識
日本の医療制度は「自由開業医制」を採用しており、医師は個人で自由にクリニックを開設できます。この制度は明治時代の「医制」に由来し、医師免許が診療行為だけでなく、開業自体の資格も認めていたことが基礎となっています。
ただし、医療法人などの法人による開設や、病床を設ける場合は、都道府県知事の事前許可が必要となることがあります。開設形態によって必要な手続きが異なるため、計画段階での確認が重要です。
診療科目については、厚生労働省の通知で過去に認められた科目の枠内であれば、麻酔科・歯科を除いて医師であれば標榜できます。たとえば、産婦人科の経験しかない医師が耳鼻科を開業することも、法律上は可能です。
以前、医師一人あたりの標榜科目を原則2科目に制限する法改正が検討されましたが、実現には至らず、現在も科目数の制限はありません。麻酔科については特別な規定があり、厚生労働大臣から「麻酔科標榜許可」を受けた医師のみが、個人名を明示して標榜できます。ただ、最近では保健所によっては指摘が入るケースもあり、標榜に問題ないかどうか、事前に行政に判断を仰いでおくと安心です。
診療所としての開設手続き
医療法では、臨床研修を修了した医師が診療所を開設した場合、10日以内に所在地の都道府県知事に届け出ることを定めています。ただし、この届出は医療法上の「診療所」としての手続きであり、保険診療を行うための要件とは別個の手続きとなります。
開設者と管理者は法律上異なる概念ですが、個人開業の場合、特別な許可がない限り、開設者である医師自身が管理者を務める必要があります。
なお、2004年3月以前に医師免許を取得し医籍登録した医師は、臨床研修修了者とみなされます。実際の届出先は、都道府県知事から権限委任を受けた市区町村長または保健所長となります。
保険医療機関としての指定
医療法上の開設届提出後、地方厚生局長に対して健康保険法に基づく「保険医療機関」としての指定申請を行います。この指定を受けることで、保険診療が可能となります。
保険診療を行う際は、医学的な診療行為と保険診療を区別し、療養担当規則に従って診療・請求を行う必要があります。一般的な手続きの流れは以下の通りです。
- 診療所開設届出(医療法・保健所)を提出。この時点で自費診療は可能
- 各月10~14日頃までに保険医療機関指定申請を提出※月毎に締め切りが決まっているため要注意
- 翌月1日付けで保険医療機関指定(保険診療開始)
- 指定通知書受領と医療機関コードの取得
指定後は、診療報酬のオンライン請求に向けて、国民健康保険連合会と診療報酬支払基金での確認試験が必要です。
開業時に提出が必要な書類一覧
医療機関の開設には、建築関連の手続きに加えて、保健所や地方厚生局への様々な申請が必要です。これらの手続きを適切なタイミングで行うことが、円滑な開業の鍵となります。以下表に開業時に提出が必要な書類一覧をまとめたので、手続き準備のご参考にしてください。
| 提出先 | 提出物 |
| 保健所 |
|
| 社会保険事務所 |
|
| 厚生局 |
|
| 労働基準監督署 |
|
| 福祉事務所 |
|
| 税務署 |
|
| 公共職業安定所 |
|
| 都道府県税事務局 |
|
| 地区医師会 |
|
開業までに行う手続きのポイント・注意点
開業までに行う手続きで、特に注意すべき点を解説します。
保険医療機関指定申請書の締め切りに間に合うようにする
保険診療を行うクリニックの開業には、まず保健所への診療所開設届(医療法人の場合は開設許可申請)の提出が必要です。その後、診療報酬を受け取るために、管轄の地方厚生局へ保険医療機関指定申請書を提出します。
この指定申請書の提出タイミングが極めて重要です。各地方厚生局では指定日と申請締切日を定めており、たとえば関東信越厚生局東京事務所の場合、毎月1日が指定日、前月10日前後が締切日となっています。10月1日開業予定の場合、9月10日頃の締切日までに申請書を提出しないと、保険医療機関としての指定が11月1日となり、1か月の開業遅延が生じる可能性があります。
そのため、保険医療機関指定申請書の提出締切日を起点として、逆算で開業スケジュールを組む必要があります。医療法上のクリニック開設だけでは保険診療ができないことに注意が必要です。
保険医療機関指定申請までには、開設届の写しを用意しておく
保険医療機関指定申請には、保健所の受付印が押された診療所開設届の写しが必要です。医療法では開設後10日以内の届出を定めていますが、実際の運用は保健所によって異なります。
多くの保健所では、実地検査を経なければ開設届に受付印を押さない独自の運用をしています。実地検査時には、医療機器や診療机、カーテンなどの備品が設置された、診療可能な状態であることが求められます。X線装置がある場合は、設置後の漏えい放射線量測定結果の提出も必要となることがあります。なお、実地検査時に必要な物品については地域によっても異なる場合があり、事前にチェック事項を保健所に聞いておくことことをお勧めします.
工事を始める前に保健所にしっかりと確認・相談しておく
建物の工事開始前に、図面を持って保健所への事前相談が必要です。この段階で相談を怠ると、実地検査時に法的には問題がなくても、保健所独自の解釈による行政指導を受ける可能性があります。その場合、工事のやり直しが必要となり、開設届の受付が遅れ、保険医療機関指定申請にも影響が出かねません。
無床クリニックの構造設備について、医療法施行規則では詳細な規定が少ないため、各自治体や保健所が独自の基準を設けていることがあります。同じ図面でも保健所によって指導内容が異なることもあり、たとえばX線操作室の設置要件などで、保健所ごとに異なる判断が示されることがあります。
さらに、同じ保健所でも担当者によって解釈が異なる場合があるため、工事前に必ず担当者に確認し、「問題ない」という明確な言質を得ておくことが重要です。これらの要件を踏まえた慎重なスケジュール立案が、スムーズな開業への近道となります。