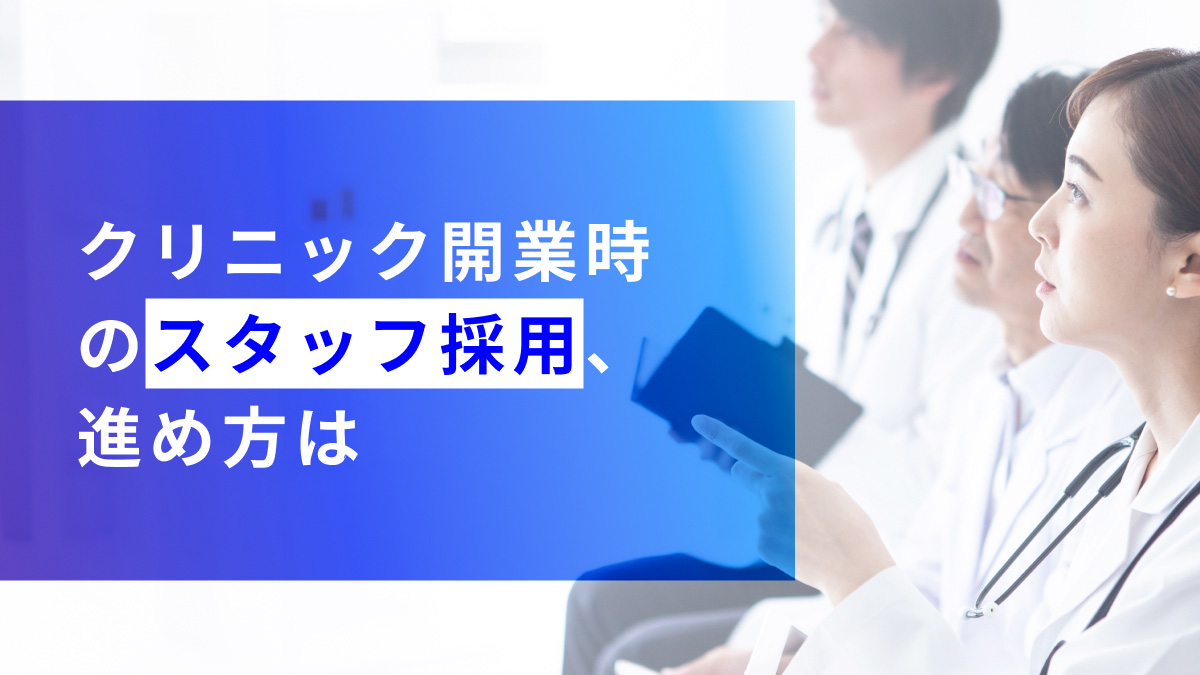
クリニック開業時のスタッフ採用、進め方や面接の手順
クリニックを開業し円滑に運営していくためには、人事や組織、マネジメントに意識を向けることも大切です。本章では、従業員の採用・面接で気を付けるべきことや、教育、労務関連で気を付けるべきことをご紹介します。
スタッフの募集方法
スタッフの募集は、多くの選択肢があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。自院に最適な方法を選ぶためには、各手段の特徴を理解し、目的に合わせて使い分けることが重要です。
ハローワーク
ハローワークを利用する最大の利点は、手続きが無料である点です。採用コストを抑えつつ、幅広い求職者に情報を届けることができます。しかし、幅広い相手に求人が届く分、選考に手間がかかるケースも。スケジュールには余裕を持たせると良いでしょう。
チラシ配布
近隣からスタッフを採用したい場合、チラシ配布も効果的です。近隣に居住しているスタッフであれば交通費を抑えられ、急な呼び出しにも対応してもらいやすくなります。自院でチラシを作成・印刷すればコスト削減につながりますが、反応率を高めるためにはプロの制作会社へ依頼するのも一手です。ただし、泌尿器科や婦人科、精神科などデリケートな診療科目では、近隣の住民がスタッフだと患者が来院しづらくなる恐れも。こうした診療科特性も意識しつつ、配布エリアを考えましょう。
民間の転職サイト、エージェント
転職サイトやエージェントを利用する場合、基本的には掲載費用や採用時の報酬が発生します。一般的には、一人あたり年収の20〜30%を支払う必要があります。コスト面の負担は大きいですが、エージェントに具体的な希望を伝えることで条件に合う人材を紹介してもらえるメリットも。
エージェントへの相談自体は無料のケースが多いため、求めるスキルや経験が十分に言語化されている場合は、相場を知るうえでも利用を検討してみると良いでしょう。
近隣の看護学校等での募集
看護学校や専門学校の就職担当者に声をかけて募集を行う方法もあります。新卒者を採用する場合、一からの丁寧な教育が必要になりますが、意欲的な若手人材を確保できるメリットがあります。将来的な成長を見据え、育成を前提とした採用を検討するのもクリニックの運営において有効です。
紹介・縁故採用
知人や関係者からの紹介で採用する方法は、信頼感があり安心して任せられます。しかし、性格やスキルに問題があっても不採用にしづらく、紹介者との関係が悪化するリスクも伴います。
また、私情に流されて厳しい指導ができない場合もあるでしょう。こうしたリスクを回避するためにも、縁故採用であっても客観的な面接を行い、適性をしっかりと見極めることが重要です。
顔なじみの看護師等
以前同じ職場で働いていた看護師を採用するケースです。
お互いを知っている安心感は大きなメリットですが、立場が変わることで新たな課題が生じることもあります。これまで同僚だった関係から、今後は雇用主と従業員になるので、勤務態度への指導や注意を行う際に軋轢が生じるかもしれません。対策としては、最初に経営者としての立場を理解してもらい、役割の違いを明確に伝えることです。また、前職の職場からの引き抜きと見なされないよう、トラブル防止にも配慮しましょう。
引継ぎ
居抜きや医院継承の場合、前任のスタッフや勤務医をそのまま雇用する方法もあります。
採用コストを抑えられ、即戦力として活躍してもらえるメリットがありますし、患者とも顔なじみであるため、信頼関係の維持にもつながります。ただし、前院長の方針をそのまま踏襲されることでスタッフに新しい経営方針に従ってもらえない可能性があります。経営理念や具体的な業務内容をしっかり伝え、適切な教育とコミュニケーションを図ることが大切です。
SNS
SNSを活用して求職者に興味を持ってもらい、応募につなげる方法も近年増えています。FacebookやX(旧Twitter)、Instagramなどで日々の情報を発信することで、クリニックの雰囲気や理念を伝えられます。ハローワークや転職サイトで応募が集まらない場合でも、SNSを通じて新たな人材と出会える可能性があります。ただし、継続的な情報発信が求められるため、運用体制を整えることが必要です。
医師の募集方法
近年は一般病院においても、縁故採用や医局からの派遣だけでは医師の確保が難しくなってきました。
そのため、民間の職業紹介事業者を活用したり、自院のホームページで直接募集したりする医療機関が増えています。これらの多様な募集手段を取り入れることで、医師の目に留まる機会が増え、採用の可能性が高まるでしょう。思うように医師が集まらない場合は、複数の媒体を活用して情報を発信することが効果的です。多様なツールを駆使することで、医師の関心を引きやすくなり、自院に適した人材を見つけやすくなります。
スタッフの採用面接時でのポイント
スタッフを採用する際の面接では、応募者の適性や意欲を的確に見極めることが重要です。初めて面接を行う場合でも、以下のポイントを押さえておくと効果的な選考ができます。
ポイント1. 面接官の側もある程度場数を踏み、採用市場の理解を
目の前の人材の市場価値や自院へのマッチ度合いを面接の場で把握するためには一定の場数も必要になってきます。
そういう意味では面接官側も面接に慣れる必要があり、質問のスキルや、自院の魅力を伝える技術を磨いたうえで、候補者とむきあうことが必要といえます。
ポイント2. 職務経歴は現在から遡って聞く
面接での質問方法に正解はありませんが、効率的に進めやすいのは「職務経歴を現在から過去に遡って尋ねる方法」。履歴書通りの順番とは逆の順序で質問することで、直近の隠れた問題点を見つけやすくなります。
これはクリニックの採用に限らず、ホワイトカラーも含めた一般論ですが、応募者は自分を良く見せようとし、都合の悪い情報を隠す傾向があります。現在から過去へ質問することで、予想外の質問に対する反応を観察でき、情報の整合性も確認しやすくなります。それにより、応募者の真の経験や能力を把握しやすくなるでしょう。
ポイント3. 職務経歴を具体的に聞く
応募者の職務経歴は評価の重要なポイントです。履歴書に記載された内容を基に、具体的な業務内容や役割を詳しく尋ねましょう。
同じ「受付・会計」を担当していたとしても、レセプトの点検や請求業務まで行っていたかどうかで、経験の深さが異なります。看護師の場合も、注射・採血ができるか、どのような検査を担当していたかなど、具体的なスキルを確認することで、即戦力として期待できるか判断できます。
ポイント4. 前職の退職理由を詳しく聞く
退職理由は、応募者の働く姿勢や価値観を知る手がかりとなります。
退職がやむを得ない事情によるものか、自己都合によるものかを見極めましょう。例えば、「正職員になれなかったから退職した」という場合、「正職員への希望を上司に伝えたか」「同僚で正職員になった人はいるか」などを質問すると、応募者の積極性やコミュニケーション能力が見えてきます。これにより、採用後に長期的に働いてもらえるかの判断材料になります。
ポイント5. スタッフの要望を聞いておく
応募者は勤務時間や働き方に関する希望を持っていることが多いです。
例えば、「扶養の範囲内で働きたい」「週に特定の日数働きたい」といった要望があります。採用後にミスマッチが起きないよう、面接時にこれらの希望をしっかりと確認しておきましょう。せっかく良い人材を採用しても、希望に合わない勤務条件では長続きしません。応募者の要望を理解し、可能な範囲で調整することで、満足度の高い雇用関係を築くことができます。
医師採用時のポイント
医院が医師を採用する際には、固定観念にとらわれず、多様なニーズに対応することが求められます。優秀な医師を確保するため、以下のポイントに注意して採用活動を行いましょう。
ポイント1. 医師の勤務ニーズの多様性を理解した訴求をする
医師は高収入が前提となるため、給与や福利厚生だけでは魅力を感じにくい場合があります。やりがいや働き方を重視する医師も多いため、病院の特色や診療方針を明確に伝えることが重要です。ワークライフバランスを重視する医師には、当直やオンコールがない勤務体系をアピールすると効果的でしょう。また、育児と仕事を両立させたい医師には、急な休みにも柔軟に対応できる環境であることを伝えると興味を持ってもらいやすくなります。
ポイント2. 医院が目指す方針を具体的に説明する
医院の理念や診療方針を具体的に示すことで、共感する医師を引き寄せることができます。ホームページや求人情報で、一人ひとりの患者に時間をかける診療を行っているのか、効率的に多くの患者を診る体制なのかを明確に伝えましょう。医師によって理想とする働き方は異なるため、自院がどのような医療を提供し、どのような役割を担ってほしいのかを具体的に示すことが大切です。
ポイント3. 医師の担当領域を明確に伝える
採用時には、医師に担ってほしい専門分野や業務内容を具体的に伝える必要があります。どの診療科を強化したいのか、既存の医師をサポートしてほしいのかなど、明確な役割を示すことで、応募者も自分のスキルやキャリアプランと照らし合わせやすくなります。また、実際に働く医師や看護師、事務スタッフから見た病院の雰囲気や働きやすさを紹介することで、よりリアルな職場環境を伝えることができます。
スタッフ雇用時のトラブル対策
スタッフの雇用時にもトラブルはつきまといます。ここでは、m3.comが実施した「院長を悩ませる問題スタッフどう対応している?」の調査結果を参考に、スタッフ雇用時のポイントを解説します。
採用時に慎重に審査する
スタッフの採用面接でのポイントとしてもご紹介しましたが、採用段階での適切な人選は、将来的なトラブル防止の基本となります。特に転職歴が多い応募者については、その理由を丁寧に確認する必要があります。面接では、クリニックの方針への理解と同意を求め、価値観の違いを早期に見極めることが重要です。採用後に方針の違いが表面化すると、スタッフの不満や患者対応の質の低下につながる恐れがあるためです。
コミュニケーション・早期対応を心がける
問題行動の予防と対応には、日常的なコミュニケーションが不可欠です。定期的な個別面談や朝礼を通じて、スタッフの考えや悩みを把握し、問題が大きくなる前に対処することが重要です。問題が発生した際は、時間を置かずに本人との対話の機会を設け、一方的な指導ではなく、本人の意見をしっかりと聞く姿勢を持ちましょう。特に職員間のトラブルでは、双方の言い分を聞き、中立的な立場を保つことで、より公正な対応が可能です。また、指導内容は記録として残し、改善が見られない場合の対応根拠として活用できるようにしましょう。
職場環境の整備
スタッフが働きやすい環境づくりは、長期的な勤続をしてもらう上だけでなく、トラブル予防においても重要です。
問題行動の背景には職場環境や業務上の課題が潜んでいることもあるためです。例えば、特定のスタッフに業務量が過度に集中しキャパシティオーバーにならないように配慮し、必要に応じて人員配置の見直しを行うことが望ましいといえます。また、定期的な業務マニュアルの見直しや、スタッフ教育の機会を設けることで、スタッフが働きづらくなっている点を解消でき、働きやすい職場環境を実現しやすくなります。長期的な視点で見れば、良好な職場環境は優秀なスタッフの定着にもつながり、組織の安定的な運営にもつながるでしょう。
- m3.com『医師はろくでなしばかり?医師の雇用で起こったトラブル』(2023年1月)
- m3.com『有料級のノウハウ満載!?「問題スタッフ対応」虎の巻』(2023年1月)
- キャククル『【医師の採用方法】欲しいドクター獲得を成功させるポイントとは?』(2022年2月)
-
5-1.建物・内装についての基礎知識
-
5-2.薬局との関係
-
5-3.診療科別レイアウト上のポイント
-
5-4.こんなクリニックはいやだ
-
5-5.内装材料の選び方
-
5-6.院内サイン
-
5-7.工事見積もり
-
5-8.工事検査
【調査概要】
院長を悩ませる「問題スタッフ」どう対応している?
回答期間: 2022年8月18日~8月24日
回答人数:m3.com医師会員 3298名