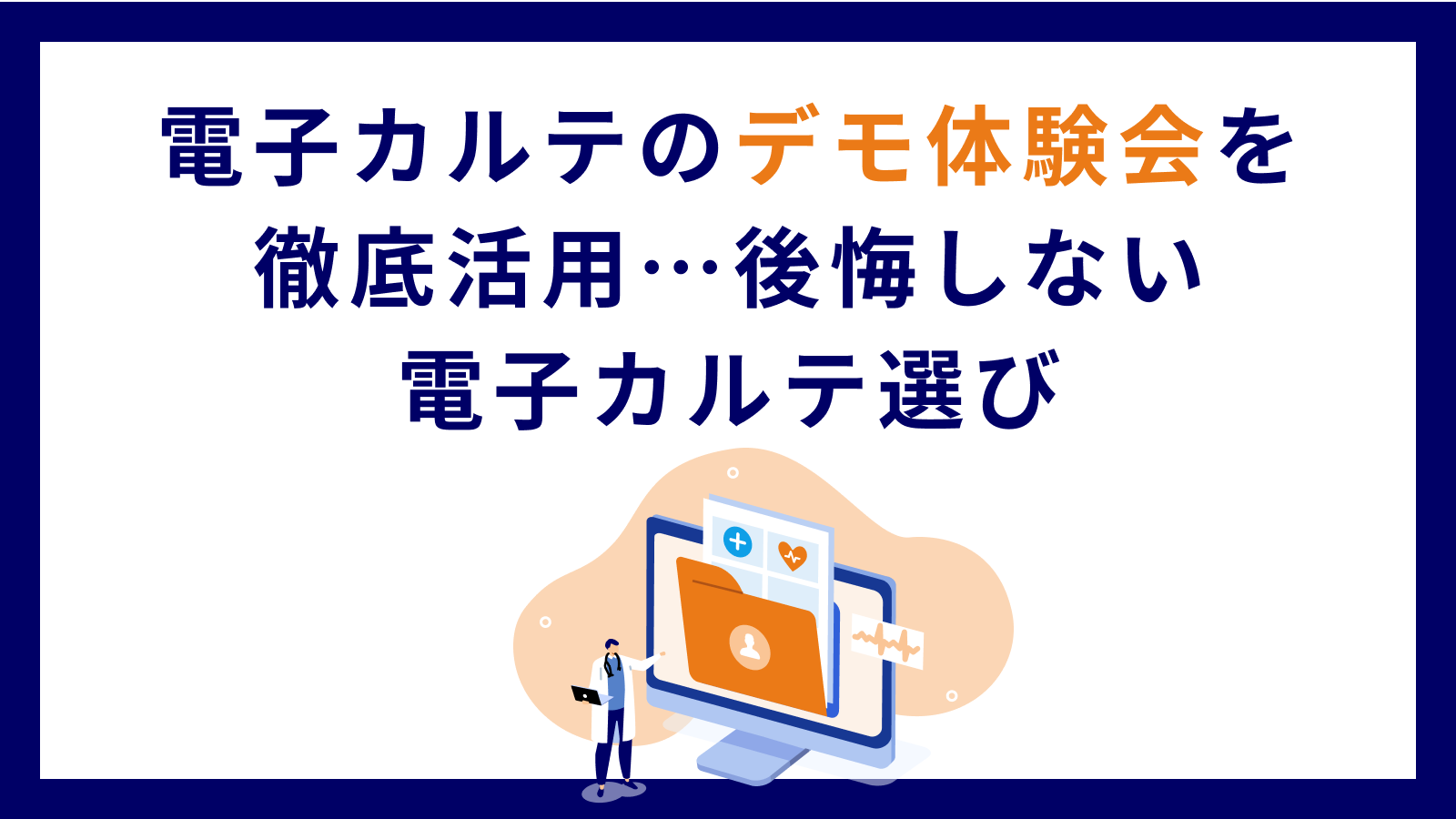
電子カルテのデモ体験会を徹底活用…後悔しない電子カルテ選び
電子カルテは医師の日々の診療業務を支える重要なツールです。しかし、市場には多種多様なシステムが存在し、カタログやウェブサイトの情報だけでは、実際の使用感や操作性を十分に把握することはできません。そこで重要となるのが「デモ体験」です。
デモ体験では実際のシステムに触れることで、操作感、機能性、連携性、サポート体制など多角的な視点から評価できます。本記事では、電子カルテのデモを最大限に活用し、後悔しないシステム選びを実現するための秘訣を詳しく解説します。
電子カルテデモの申し込み方法と準備
デモの種類と申し込み先
基本的には各ベンダーのウェブサイトからデモの申し込みが可能で、多くの場合、問い合わせフォームから応募すると各社のフローにのっとって対応してもらえます。多数の電子カルテメーカーが、資料請求に加えてデモサービスを提供しているため、複数のベンダーに申し込んで比較検討することをお勧めします。
デモ前の準備:明確にしておくべきニーズ
デモ体験を最大限に活用するためには、事前準備が不可欠です。まず、自院が電子カルテに求める機能や解決したい課題を明確にしておきましょう。例えば、診療の効率化、オンライン診療への対応、患者コミュニケーションの向上など具体的な目的をリストアップします。現在使用しているシステムがあれば、その課題点や不満な点も整理しておくと、新しいシステムに求める要件をより明確にできます。
デモに持参すべき資料とスタッフ
デモ当日は、現在使用している紙カルテや電子カルテの画面のサンプル、診療の流れを示す資料、そして既存のシステムや機器のリストを用意しておくと、具体的な連携の可能性などを確認しやすくなります。また、可能であれば実際にシステムを使用する看護師や受付スタッフなども同席させると、多角的な視点で評価できます。
デモ体験で必ずチェックすべき7つのポイント
1. 操作性と画面デザイン
電子カルテは毎日長時間使用するツールであるため、操作性は特に重要です。開業準備中のある医師は「とにかくいろいろな電子カルテを直接使って確認したい」と操作性を重視しています。デモでは、画面の見やすさ、メニューの分かりやすさ、必要な情報へのアクセスのしやすさなどを確認しましょう。特に診療中の画面遷移がスムーズか、クリック数が少なく済むかをチェックすることが重要です。
2. 入力効率とテンプレート機能
カルテ入力の効率性は業務全体のスピードに直結します。カルテ1枚あたり数十秒の違いでも、1日、1ヶ月で考えると大きな差になるものです。デモでは実際に患者情報を入力するシミュレーションを行い、テンプレート機能や音声入力機能、ショートカットキーなどの使いやすさをチェックしましょう。自院の診療科に特化したテンプレートがあるか、カスタマイズは容易かも重要なポイントです。
3. 他システムとの連携性
予約システム、会計システム、レセプトシステム、検査機器など、他のシステムとの連携がスムーズかどうかは重要なチェックポイントです。デモでは、現在使用しているシステムや導入予定の機器との連携が可能かを具体的に確認しましょう。連携が不十分だとデータの二重入力が必要となり、かえって業務効率が低下する可能性があります。特にレセプト連携はスムーズさを実際に確認することをお勧めします。
4. サポート体制と導入トレーニング
電子カルテ選びにおいて多くの医師が重要視するのが「サポート」体制。システムに不具合が発生した場合、迅速な対応がなければ診療業務が滞ってしまう可能性があるためです。デモ体験ではサポートの対応時間、連絡方法(電話、メール、リモートなど)、導入トレーニングの内容と期間を詳しく確認しましょう。担当者の対応の丁寧さもサポート品質を判断する重要な指標となります。
5. クラウド型とオンプレミス型の比較
近年人気が高まっているクラウド型電子カルテと従来のオンプレミス型には、それぞれメリット・デメリットがあります。クラウド型は初期費用が比較的安価で導入期間も短い傾向にある一方、月額費用が発生します。オンプレミス型は初期費用が高額になる傾向がありますが、カスタマイズ性が高く、基本的に月額費用は発生しません。デモではそれぞれの特性を踏まえ、自院の運用スタイルやIT環境に合った選択ができるよう確認しましょう。
6. セキュリティ対策
患者情報を扱う電子カルテでは、セキュリティ対策も重要な確認事項です。デモではID・パスワード管理、アクセス権限の設定方法、データバックアップ体制、暗号化の有無などを確認しましょう。特にクラウド型を検討する場合は、サーバーのセキュリティ対策やデータの保護方法についても詳しく質問することをお勧めします。
7. 費用と導入スケジュール
デモでは初期費用と運用コストの両方を明確にしてもらいましょう。初期費用にはハードウェア費用、ソフトウェアライセンス料、導入支援費用、トレーニング費用などが含まれます。運用コストには保守料、サポート料、バージョンアップ料などがあります。また、導入から実際の運用開始までのスケジュールも確認し、円滑な移行が可能かを評価することが重要です。
失敗しないデモの受け方と効果的な質問例
デモ当日の効果的な進め方
デモ当日は、説明を聞くだけでなく、実際に自分で操作してみることが重要です。基本操作から応用機能まで、実際の診療シナリオを想定しながら試してみましょう。例えば、新患登録から問診、診察、処方、会計までの一連の流れを体験することで、システムの使い勝手を実感できます。また、自分の診療科特有の処置や検査のシミュレーションも重要です。
具体的な質問例
デモでは以下のような具体的な質問をすることで、システムの詳細を把握できます。
- 「自院の診療科に特化した機能はありますか?」
- 「現在使用している〇〇(具体的なシステム名)との連携は可能ですか?」
- 「データ移行はどのように行われますか?費用はかかりますか?」
- 「サポート体制について、緊急時の対応時間や平均対応速度を教えてください」
- 「カスタマイズはどの程度可能ですか?費用や期間はどのくらいかかりますか?」
- 「将来的なバージョンアップの頻度と費用はどうなっていますか?」
- 「他の医療機関との情報連携はどのように行えますか?」
- 「障害発生時のバックアップ体制はどうなっていますか?」
複数メーカーのデモ受講時の比較ポイント
複数のメーカーのデモを受ける場合は、同じチェックリストを使用して比較することをお勧めします。特に操作性、入力効率、サポート体制、費用面などの重要項目について5段階評価するなど、客観的に比較できる方法を用意しておくと良いでしょう。デモ直後に評価を記録することで、後から比較検討する際に記憶が曖昧になることを防げます。
デモ後の比較評価方法
評価シートの作成方法
複数のシステムを比較検討するためには、評価シートを作成すると効果的です。以下の項目を5段階評価するなどして客観的に比較しましょう。
- 操作性・使いやすさ
- 入力効率・操作スピード
- 画面デザインの見やすさ
- 機能の充実度(診療科特有の機能含む)
- 他システムとの連携性
- サポート体制の充実度
- 初期費用と運用コスト
- 導入スケジュールの実現性
- セキュリティ対策の充実度
- カスタマイズの自由度
重視すべきポイントの優先順位付け
評価項目には自院の状況に応じて重み付けをすることをお勧めします。例えば、サポート体制を特に重視する場合はその項目に2倍の重みを付けるなど、優先順位を明確にすることで、自院に最適なシステムを選びやすくなります。ある開業医は「多少コストがかかっても、サポート体制が充実しているシステムを選ぶ」と決断しましたが、これは自院の優先順位をしっかりと見極めた結果といえるでしょう。
デモ体験と実際の運用ギャップを埋める方法
デモ環境と実際の運用環境には差があることも念頭に置いておきましょう。できれば既にシステムを導入している同規模・同診療科のクリニックの使用状況も参考にすることをお勧めします。ベンダーに導入実績のあるクリニックの紹介を依頼するか、医師会などのネットワークを通じて情報収集すると良いでしょう。実際のユーザーからは、デモでは分からなかった長期使用における利点や課題が聞けることがあります。