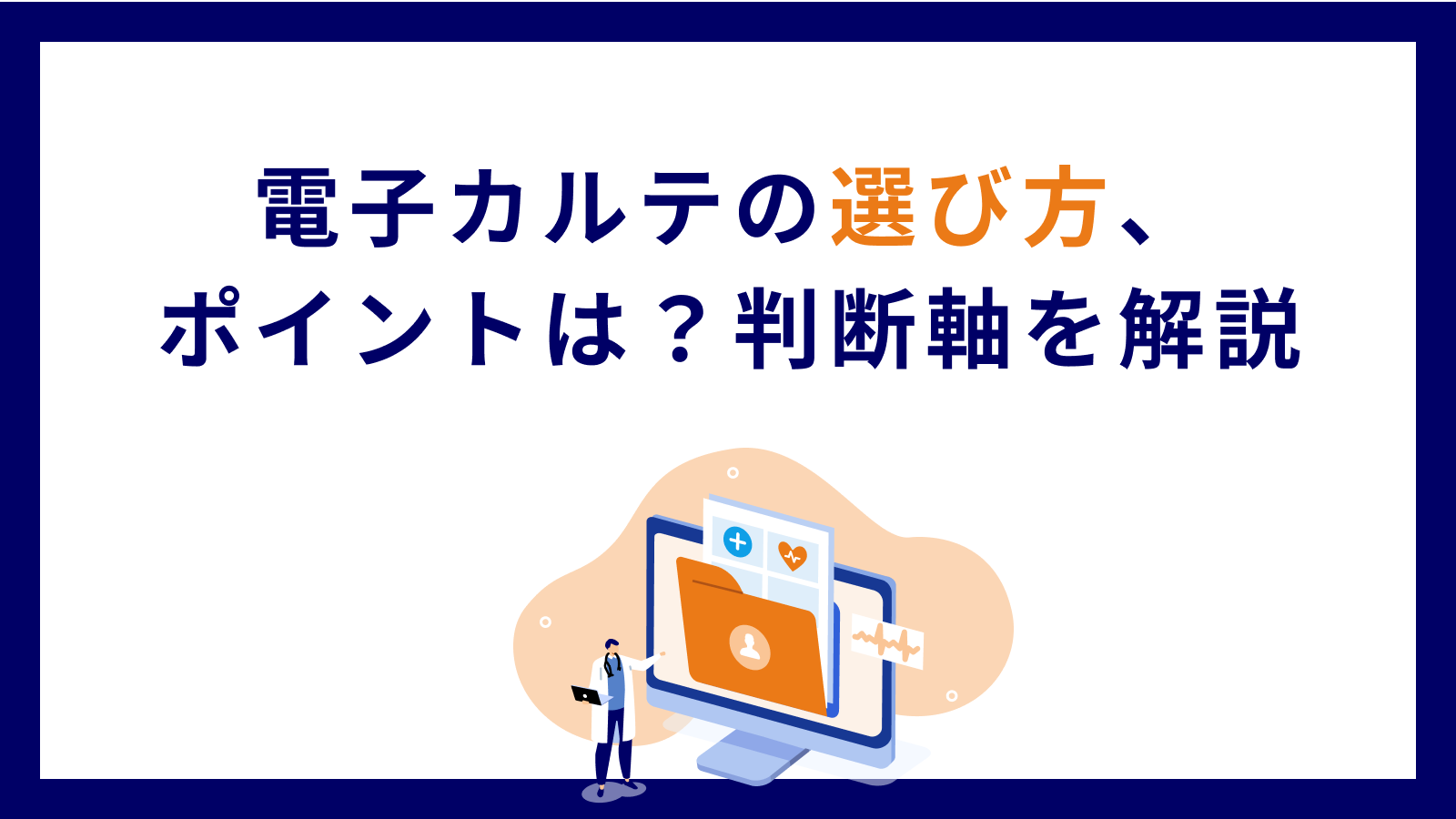
電子カルテの選び方、ポイントは?判断軸を解説
電子カルテは医療機関の効率向上と患者ケアの質を高める重要な投資です。しかし、市場には様々なシステムが存在し、最適な選択をするのは容易ではありません。本記事では、開業医が電子カルテを選定する際に考慮すべき重要なポイントを、実際の選定基準のデータと共に詳しく解説します。
電子カルテ選定時の優先項目:医療機関の声
医療機関が電子カルテを選ぶ際に重視するポイントは多岐にわたります。m3.comが実施したデータによれば、最も重視される要素は価格(13.6%)であり、次いで充実したサポート体制(12.0%)が続きます。さらに、自身の診療スタイルに合わせられるカスタマイズ性(7.8%)や他の診療機器・システムとの連携(7.5%)も重要視されています。セキュリティの信頼性(6.6%)やカルテ入力の所要時間(6.3%)、レセコン一体型(6.3%)といった要素も選定に大きな影響を与えています。
| 選定基準 | 優先度(%) |
| 価格 | 13.6% |
| 充実したサポート体制 | 12.0% |
| 自身の診療スタイルに合わせられるカスタマイズ性 | 7.8% |
| 他の診療機器・システムとの連携 | 7.5% |
| セキュリティの信頼性 | 6.6% |
| カルテ入力の所要時間 | 6.3% |
| レセコン一体型 | 6.3% |
| クラウド型であること | 6.2% |
| ハードやソフトの更新・買い替えが不要なこと | 6.0% |
| 企業への信頼性 | 5.3% |
| 診療科や施設規模への適応度 | 4.4% |
| 画面デザイン | 2.7% |
| 災害対策 | 2.7% |
| 導入件数 | 2.4% |
| ORCA連携 | 2.1% |
| 補助金対象 | 2.0% |
| 在宅・往診への適応度 | 1.9% |
| その他 | 1.5% |
| 知人のすすめ | 1.5% |
| オンプレ型(院内サーバー設置型)であること | 1.1% |
電子カルテの基本:オンプレミス型とクラウド型
電子カルテには大きく分けて「オンプレミス型」と「クラウド型」の二種類があります。それぞれの特徴を理解し、自院に最適なタイプを選びましょう。
オンプレミス型:安定性とカスタマイズ性
オンプレミス型は電子カルテとしての歴史も古く、多くの大学病院や市中病院で採用されています。院内にサーバーを設置し、自院内で電子カルテ情報を管理するシステムです。
オンプレミス型の最大の魅力は手厚いサポート体制にあります。多くの大手メーカーは多数の代理店を持ち、電子カルテ導入時の操作研修、開業時の立ち合い、レセプトオンライン請求の補助など、対面でのサポートが受けられます。これはパソコンが苦手な医師やスタッフにとって大きな安心材料となるでしょう。また、機能も充実しており、医院のニーズに合わせた細かなカスタマイズが可能です。
主な代表製品としては、無床診療所向け電子カルテシェアNo.1のPHC社(Medicom-HRV)や、富士通社(HOPE LifeMark-SX)、キヤノンメディカルシステムズ社(TOSMEC Aventy3.0)などが挙げられます。
一方で、検討すべき点として、購入費用と月額費用に加え、パソコンの耐用年数の関係で約5年ごとの機器買い替えが必要になるなど、クラウド型と比較すると費用面での負担が大きくなる傾向があります。導入を検討する際には初期費用の差だけでなく、長期的な運用コストも含めた総合的な視点が重要です。
クラウド型:コスト効率とデータセキュリティ
近年人気が急上昇しているクラウド型電子カルテは、インターネット上のサーバーでデータを管理するシステムです。インターネットのブラウザを利用して電子カルテを使用するため、特別な設備投資が少なく、初期費用を抑えられるメリットがあります。また、パソコンの買い替えも自院で自由に選択できるため、長期的なコスト面でも優位性があります。
サポート面では、従来はメールや電話、チャット機能などが中心でしたが、最近ではエムスリーデジカル社(M3 DigiKar)のように、オンプレミス型と同様に対面でのサポートプランを用意しているメーカーも増えています。
セキュリティ面についても、クラウド型電子カルテが使用しているクラウドは、アクセス回線もネットバンキングと同様に高いセキュリティレベルで管理されており、情報管理の信頼性は高いと言えます。さらに、データバックアップの観点からも優位性があります。サーバーは日本国内の複数箇所に分散されているため、災害などでどこかの地域でサーバーが被害を受けても、別のサーバーからデータを取得できるリスク分散が実現されています。
ただし、カスタマイズ性においては、オンプレミス型の方が柔軟性が高い傾向にあります。レイアウトなどを細かく自分好みに設定したい医師には、オンプレミス型の方が適しているかもしれません。
電子カルテ選定の重要基準:成功への道標
電子カルテを選定する際には、オンプレミス型かクラウド型かという選択に加えて、以下の重要な基準を念頭に置くことが大切です。
医療連携の要となる「相互運用性」
相互運用性とは、他の医療機関や地域医療連携ネットワークとの情報共有能力を指します。今後の医療連携の推進を考えると、単に院内での使いやすさだけでなく、地域全体の医療ネットワークとの連携可能性も重要な選定基準となります。データの標準規格対応やAPI連携の柔軟性は、将来的な拡張性を左右する重要な要素です。
患者が他の医療機関を受診した際に、スムーズに診療情報を共有できるシステムであれば、重複検査の回避や適切な治療方針の迅速な決定が可能になります。特に地域包括ケアが推進される中、病院、診療所、薬局、介護施設などとの情報連携は今後ますます重要性が高まるでしょう。患者紹介・逆紹介時の情報共有のしやすさも、日常診療の効率化に直結します。
セキュリティの堅牢さ
電子カルテシステムでは、患者の機密性の高い情報を安全に管理し、データ侵害のリスクを最小限に抑える必要があります。個人情報保護法の遵守はもちろん、保存時および転送中のデータ暗号化、強固なアクセス制御、定期的なセキュリティ監査など、多層的な防御策が求められます。
特に注目すべきは、不正アクセス防止対策です。強力なパスワードポリシーの設定、二要素認証や多要素認証の導入、職務責任に基づいたアクセス制限、監査ログによる操作履歴の追跡など、総合的なセキュリティフレームワークが整っているかどうかを確認しましょう。
セキュリティ対策は決して妥協できない要素です。患者データの漏洩は、医療機関の信頼を著しく損なうだけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。ベンダーのセキュリティへの取り組みを詳細に評価し、定期的なセキュリティアップデートやパッチ適用が確実に行われるかどうかも確認することが大切です。
長期的視点での費用対効果
電子カルテシステムの導入には、初期費用、運用費用、保守費用など様々なコストが発生します。しかし、単に価格の安さだけで判断するのではなく、業務効率の向上やエラー削減、患者ケアの質の向上といったメリットとのバランスを考慮した費用対効果の視点が重要です。
導入費用には、ソフトウェアライセンス料、ハードウェア費用、インストールおよび設定費用、データ移行費用、スタッフ研修費用などが含まれます。運用費用には、ソフトウェアサブスクリプション料(クラウド型の場合)、ITインフラのメンテナンス費用(オンプレミス型の場合)、通信費用などがあります。更新費用としては、バージョンアップ費用やハードウェア更新費用も考慮する必要があります。
クリニックを20年運営すると考えた場合、初期費用の差よりも長期的な運用コストの差の方が総支出に大きな影響を与えることが多いです。複数のベンダーから詳細な見積もりを取得し、5年、10年、20年といった長期的な視点での総所有コストを比較検討することをお勧めします。
操作性:全スタッフにとっての使いやすさ
電子カルテは医師だけでなく、看護師、医療事務スタッフなど、様々な職種のスタッフが日常的に使用するツールです。全てのユーザーにとって直感的で使いやすいインターフェースを備えたシステムを選ぶことが、スムーズな運用の鍵となります。
特に診察中は患者と向き合いながら効率的にデータ入力ができることが重要です。カスタマイズ可能なテンプレートやショートカット機能、音声入力などの効率的な入力方法が用意されているかどうかをチェックしましょう。また、各職種の業務フローに合わせた画面構成や機能が整っているかも重要なポイントです。
可能であれば、導入前にデモ環境やトライアル期間を利用して、実際の診療シーンを想定した操作性の確認を行うことをお勧めします。この際、医師だけでなく、看護師や受付スタッフなど、実際にシステムを使用する全てのスタッフの意見を聞くことが大切です。
まとめ:最適な電子カルテ選択のために
電子カルテの選定は、医療機関の長期的な業務効率と患者ケアの質に大きく影響します。価格だけでなく、サポート体制、カスタマイズ性、セキュリティ、操作性など多角的な視点で比較検討することが重要です。また、オンプレミス型かクラウド型かの選択は、医院の規模や運営スタイル、ITリテラシーなどを考慮して決定しましょう。
複数のベンダーからデモや見積もりを取得し、同じ条件で比較することで、自院に最適な電子カルテシステムを見つけることができるでしょう。選定プロセスに時間をかけることは、長期的に見れば必ず報われる投資となります。最終的には、医療の質向上と業務効率化の両立を実現するシステムが、貴院にとっての最適な選択となるはずです。