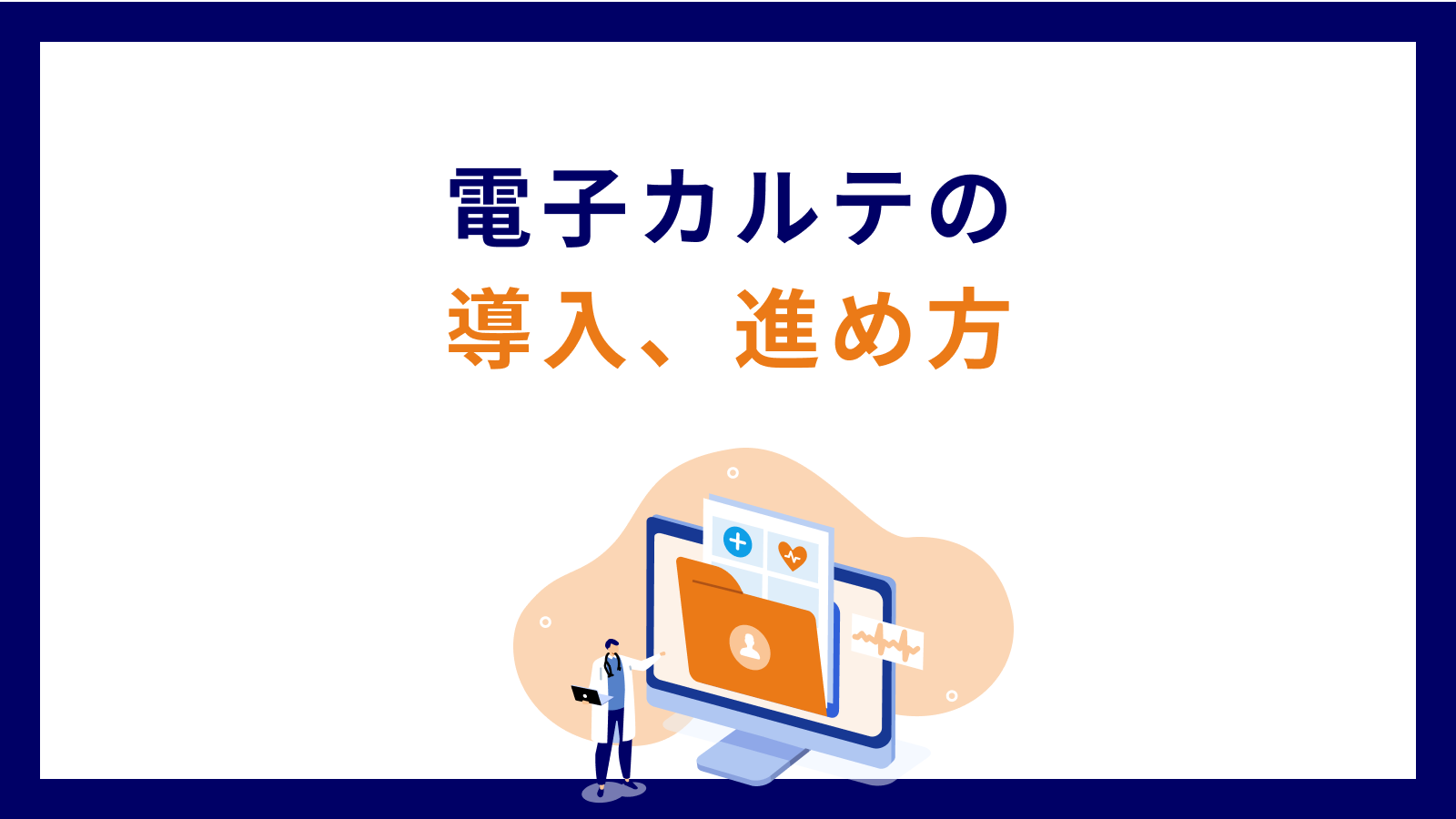
電子カルテの導入、進め方
令和5年医療施設によると、診療所における電子カルテ導入率は55%。政府も2030年までに電子カルテ普及率100%を目指す方針を示しており、すでに多くの医師が電子カルテ導入に踏み切っている一方、「導入の手間やコスト」を理由に躊躇しているケースも少なくありません。
事前に具体的な手順やスケジュールを把握しておけば、スタッフ教育やコスト管理が行いやすくなるため、導入時の混乱を最小限に抑えることが可能です。今回は導入までの全体像を「1~2か月程度」で進めるモデルケースを紹介しながら、準備のポイントを解説していきます。
電子カルテ導入の全体スケジュールと準備の流れ
導入までの流れ(モデルケース)
- 検討・情報収集(~導入2か月前)
- 事前ヒアリング・機種選定(導入2か月前)
- 導入契約・環境準備(導入1~1.5か月前)
- スタッフ研修・動作テスト(導入1か月前~2週間前)
- ロールプレイで最終確認(導入2週間前~直前)
- 本稼働スタート(導入当日~)
今回はある程度標準的な事例として「約2か月を目安」にしていますが、院内の規模やスタッフの習熟度によっても当然トータルとしての期間は前後します。どのようなタイムスケジュールで行うにせよ、それぞれのフェーズで誰が何を担当するかを明確にしておくことが重要です。
ステップ別チェックポイント
検討・情報収集(~導入2か月前)
まずは導入目的を整理するところから始めます。一口に電子カルテといっても種類は様々であり、受けられる恩恵にも濃淡があります。まずは以下のように目的を明確にしたうえで、どのメーカー・システムが目的に合致するかを情報収集しましょう。
- 紙カルテの保管・検索負担を減らしたい
- 国の電子カルテ化方針に合わせたい
- クリニックのDX(オンライン予約・オンライン診療など)を見据えたい
近年はクラウド型の電子カルテが注目されており、オンプレ型(院内サーバー型)と比較して初期費用が抑えられ、更新コストもかかりにくいという特徴があります。オンラインや展示会などを活用して、候補となる製品・サービスをいくつかピックアップしておくと良いでしょう。
事前ヒアリング・機種選定(導入2か月前)
メーカーや販売代理店に問い合わせ、実際にクリニックの運用イメージを伝えながら導入プランを作成していきます。もしレセプトコンピューター(レセコン)をすでに運用している場合は、そのレセコンとの連携が可能かどうか、費用面と操作面の両方で確認してください。
この段階では特に、スタッフが操作に慣れるまでの教育サポートの充実度や、実際に発生する費用(初期費・月額費・バージョンアップ費など)の内訳を明確にしておくことが大切です。それらも踏まえたうえでこの段階で見積もりを比較検討し、最終的に導入する機種とプランを決定します。
導入契約・環境準備(導入1~1.5か月前)
導入機種が決まったら、正式契約を結び、メーカー側で端末の設定やシステム構築がスタートします。
クラウド型の場合はインターネット環境の見直しやWi-Fiルーターの整備が必要になる場合もあるため、同時並行で院内ネットワークを最適化しておきましょう。
また、紙カルテを多く保管している場合は、必要に応じて保管ルールの見直しやスキャン代行サービスの利用などを計画しておくと、電子カルテ稼働後の運用がスムーズになります。
スタッフ研修・動作テスト(導入1か月前~2週間前)
導入予定日の約1か月前からは、スタッフ向けの研修を本格的に始めます。メーカーによってはオンライン研修に加えて訪問サポートを実施してくれるケースもあるため、可能なかぎり活用してください。研修では、
- 電子カルテでのカルテ記載方法
- オーダー入力やレセコンとの連携手順
- 問診・診察・会計などの各業務フローのシミュレーション
など、実際の業務が想定されるトレーニングを中心に行います。院長だけでなく、受付スタッフや看護師・検査技師など「誰がどこまで操作を覚える必要があるのか」を明確にし、それぞれ担当区分ごとに教育を進めると理解が深まりやすくなります。
ロールプレイで最終確認(導入2週間前~直前)
導入2週間前を目安に、実際の診療フローを模したロールプレイで最終確認を行います。想定患者数を決め、受付から診療、会計まで一連の流れを通して操作ミスや疑問点を洗い出すことで、本番直前に不安要素を解消できます。
紙カルテからの移行期間を設けたい場合は、この時点で「紙+電子カルテの併用」をシミュレーションしてみましょう。段階的に電子カルテ使用者(患者さんの一部)を増やしていくことで、スタッフや院長自身が無理なく新しいシステムに慣れていけます。
本稼働スタート(導入当日~)
ロールプレイで問題がなければ、いよいよ本番稼働です。導入初日はクリニック全体が落ち着かないことが多いため、できればメーカー担当者やシステムサポートの連絡先を院内に周知し、何かあれば即座に問い合わせられる体制を用意しておきましょう。
稼働後1~2週間は予想外のトラブルやスタッフの不慣れにより、多少の混乱が起きることもあります。ただし、導入前の研修とロールプレイをしっかり行っていれば、大きな問題に発展することは少ないはずです。徐々に操作を覚えていき、1か月程度で安定稼働に移行するケースが一般的です。
費用・運用面で確認すべきポイント
初期費用と月額費用の内訳を明確に
電子カルテの価格設定は、オンプレ型かクラウド型かによって大きく異なります。オンプレ型では院内サーバーや専用端末の購入に高額な初期投資が必要な一方、クラウド型なら初期費用0円から導入できる場合もあるため、予算に合わせて比較検討してください。月額費の中にどこまでサポートやバージョンアップ費が含まれているのか、しっかりと確認しておきましょう。
サポート体制とバージョンアップの頻度
導入後の運用サポートが充実しているかどうかは、電子カルテを長く使い続けるうえで非常に重要です。オンライン・電話サポートの受付時間や、必要に応じた訪問サポートの可否など、対応範囲を契約前に確認しておきましょう。クラウド型の場合は、バージョンアップが自動で行われたり、常に最新の機能を使えたりする点も大きな魅力です。
紙カルテとの併用・過去データの管理方法
スタッフの抵抗感を減らすためには、「紙カルテと新しい電子カルテを併用する期間を設ける」「過去のカルテ履歴をどう電子化するか」など、運用を定着させるまでの動き方について早めに検討しておくと安心です。全データを一気に電子化する必要があるのか、一部をスキャンするだけで運用できるか、などクリニックの方針に合わせて進めましょう。
電子カルテ導入を成功させるためのポイント
導入スケジュールを明確にしても、実際に運用が定着するまでは院内の協力が不可欠です。スタッフとのコミュニケーションを十分に図り、以下の点を特に意識してみてください。
-
スタッフの不安を取り除く
操作説明を繰り返すだけでなく、導入後の業務メリットを共有することでモチベーションを上げる。 -
段階的な移行も検討
一気に100%デジタル化せず、患者さんやスタッフの状況を見ながら紙カルテとの併用期間を設定する。 -
サポート窓口の周知
困った時にすぐ相談できる環境を整えておくことで、大きな混乱が起きづらい。
こうしたポイントを押さえておくと、スムーズに運用を立ち上げることができ、結果的に診療の効率化や患者さんの満足度向上につながります。
計画的な手順で導入すれば、2か月ほどでも稼働可能
以上のように電子カルテは、正しいステップを踏んでスタッフや院長が納得した状態で導入すれば、約2か月の準備期間でも十分本稼働にこぎ着けられます。
- 目的と予算を明確にする
- システム選定とサポート内容の確認を丁寧に行う
- 研修とロールプレイで本番環境をシミュレーションする
上記の流れをしっかり踏まえることで、導入時のトラブルや混乱を最小限に抑えられるはずです。
政府の「2030年までに電子カルテ普及率100%」を目指す方針も追い風となり、これからは新規開業のタイミングでも、既存クリニックの運用改善でも、電子カルテ化が加速していくと考えられます。紙カルテからの転換期にあたって、多くの先生が導入手順を正しく理解し、トラブルなくスムーズに電子カルテを使い始められるよう願っています。ぜひ今回の記事を参考に、具体的なスケジュールや準備を早めに検討してみてください。