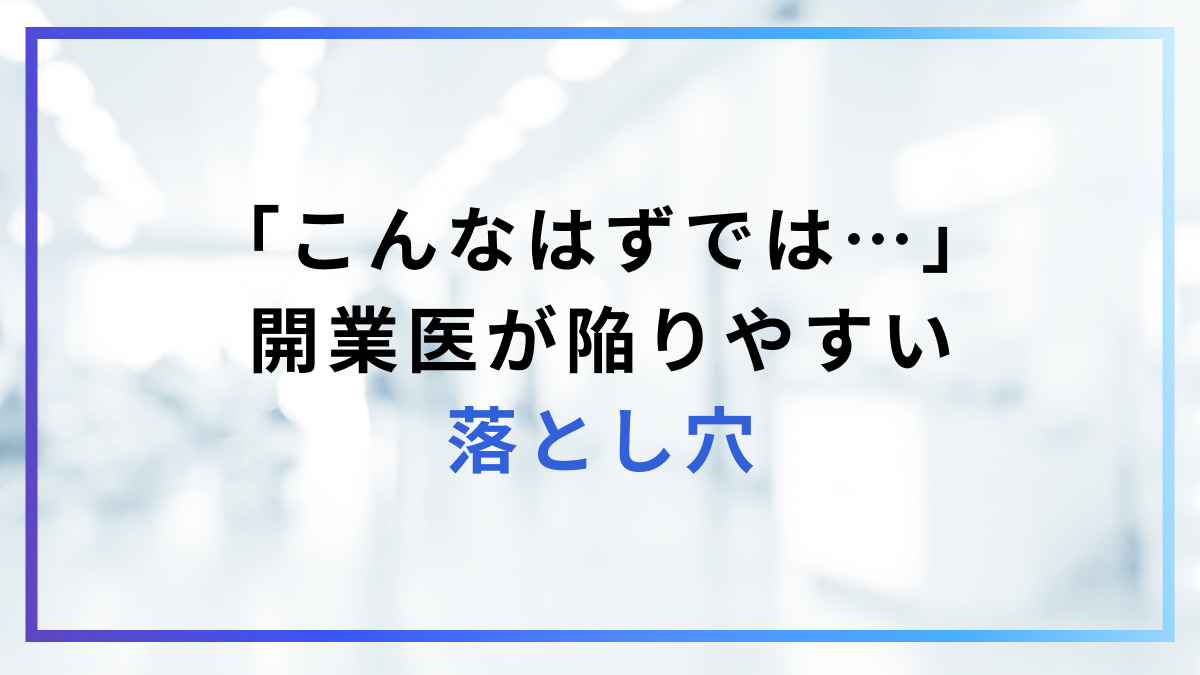
「こんなはずでは…」開業医が陥りやすい落とし穴
開業に至るまでは細やかな準備が必要となりますが、過去の失敗事例から学び、開業準備から日々の運営に至るまで、注意すべき点を理解しておくことで、思わぬ落とし穴に落ちる心配がぐっと減ります。本記事では、開業医が陥りやすい「NGポイント」を多角的に解説し、それぞれの対策を解説します。
開業準備段階でのNGポイント
資金調達の失敗
クリニック開業において、資金調達は最初の、そして最も重要なステップの一つです。計画の甘さや見通しの誤りから、資金調達に失敗し、開業自体が頓挫したり、開業後に経営難に陥ったりするケースが少なくありません。失敗しないためには、必要資金を正確に見積もり、適切な調達方法を選択することが重要です。
運転資金不足
開業資金として最初に思い浮かぶのは、物件取得費や医療機器購入費ですが、見落としがちなのが開業後の運営に必要な運転資金です。開業初期は、まだクリニックの認知度が低いため、患者数が安定するまでに時間がかかるのが一般的です。その間も、家賃、人件費、光熱費、医療材料費、医療機器のリース料など、固定費は容赦なく発生し続けます。特に保険診療の場合、診療報酬が実際にクリニックに入金されるまでには1〜2ヶ月のタイムラグが生じるため、この期間をどう乗り切るかが課題となります。
多くの開業医が陥る失敗は「開業さえすれば患者はすぐに来る」という楽観的な見通しです。実際には、新規開業のクリニックが地域に浸透し、安定した患者数を確保するまでには3ヶ月から半年、場合によっては1年以上かかることもあります。この間の運転資金が不足すると、日々の支払いに窮し、最悪の場合、黒字倒産という事態も起こりかねません。
対策:
事業計画を策定する際には、収入が安定するまでの期間を考慮し、少なくとも半年分、できれば1年分の運転資金を見積もっておきましょう。また、予期せぬ設備修理や追加購入が必要になるケースも考慮し、さらに余裕を持った資金計画を立てることが重要です。金融機関からの融資だけでなく、自己資金や医療機関専門のファクタリングサービスなど、複数の資金調達手段を組み合わせることも検討しましょう。
過剰な設備投資
最新の医療機器を揃えることは、質の高い医療を提供するために重要ですが、開業初期に過剰な設備投資を行うことは、資金繰りを圧迫する大きな要因となります。医療機器は高額なものが多く、導入には多額の資金が必要です。また、最新機器は機能が優れている反面、導入コストだけでなく、維持費やランニングコスト、消耗品費用も高くなる傾向があります。
開業時は理想の医療空間を実現したいという気持ちが先行し、必要以上に最新設備を導入しがちです。「患者に最高の医療を提供したい」「他院との差別化を図りたい」という思いから、高額な検査機器や治療機器を一度に揃えてしまうケースが少なくありません。しかし、実際に開院してみると、やってくる患者さんは一般内科の範疇だったりすることも珍しくなく、稼働率が低い医療機器ばかりを揃えてしまうと、投資回収が進まず、経営を圧迫するだけでなく、院内のスペースを狭めてしまう可能性もあります。
なお、診療科によっても必要な設備は大きく異なります。例えば、小児科や心療内科では比較的初期投資が抑えられる一方、整形外科やレントゲン設備を多用する診療科では高額な機器が必要になります。自分の診療科に本当に必要な機器は何か、患者数や症例からみて投資回収が見込めるかを冷静に判断することが重要です。
対策:
開業初期は必要最低限の設備に留め、経営が安定し、収益が上がってから徐々に必要な機器を導入していくのも一つ。また、リースやレンタルを活用することで、初期費用を抑えることができます。機器選定の際は、初期費用だけでなく、ランニングコスト、保守費用、消耗品費用なども含めたトータルコストを計算し、投資回収計画を立てることが重要です。同時に、将来的な診療拡大を見据えた設備計画も考慮しておきましょう。
甘い資金計画と管理
開業資金の見積もりや開業後の資金管理が甘いと、予期せぬ費用の発生に対応できず、経営が立ち行かなくなる可能性があります。クリニック経営は、医療行為を提供するだけでなく、事業として収益を上げ、支出を管理していく必要がありますが、どうしてもここの計画は、甘くなりがちです。
よくある失敗例として、建築費や内装費が当初の見積もりを大幅に上回るケースがあります。内装工事は追加工事や仕様変更が頻繁に発生し、当初の見込みよりも大幅に増加することが珍しくありません。また、開業後のクリニックの収益がそのまま自身の生活費となる場合、住宅ローンなどの個人的な支出も考慮に入れた現実的な収支計画を立てる必要があります。
自分の専門分野の診療は売上が高いから、初期投資はすぐに回収できる」「この地域には同じ診療科がないから患者は確実に集まる」といった安易な考えも危険です。どんなに魅力的なクリニックでも、認知されるまでには時間がかかります。また、見込んでいた患者層とは違う層が来院母数の大半を占めると、当初の見込みは大きくずれてきます。患者数や単価を予想した綿密な事業計画を立て、できるだけ厳しい条件を設定しておくのが基本です。
対策:
専門家(税理士、医療経営コンサルタント、ファイナンシャルプランナーなど)の助けを借りながら、現実的で詳細な資金計画を作成しましょう。収入と支出を正確に予測し、余裕を持った資金繰り計画を立てることが重要です。特に開業後3〜5年間の中期的な収支計画は必須です。また、月次で収支状況を確認し、計画との乖離があれば早急に対策を講じる習慣をつけましょう。なお、金融機関との関係構築も重要です。開業前から定期的にコミュニケーションを取り、信頼関係を築いておくことで、急な資金需要にも対応しやすくなります。
物件選定の失敗
クリニックの成否を大きく左右する要素の一つが、物件の選定です。立地条件が悪ければ、どれだけ優れた医療を提供しても患者は集まりません。物件選定は開業において最も重要な決断の一つであり、一度決めると簡単には変更できないため、慎重に検討する必要があります。
集患力の低い立地
言うまでもなく、交通の便が悪い場所、競合するクリニックが多いエリア、ターゲットとなる患者層が少ない地域などを選んでしまうと、期待通りの集患が難しくなります。患者は、体調が優れない状況でクリニックを受診することが多いため、アクセスしやすい場所を選ぶ傾向があります。特に高齢者や子連れの患者さんは、移動の負担が少ない場所を選びます。
「元々所有している土地があるから」「家賃が安いから」という理由だけで安易に立地を決めてしまうケースが見受けられますが、これは大きな落とし穴となり得ます。また、大通りから見えにくい場所や入りづらい路地にある物件も避けられるとベターと言えます。クリニックは「何をやっているのか分かりやすく」「入りやすい」場所にあることが集患の基本条件とされるからです。
そのほか「避けたほうが良い」とされがちなのは、駅から遠すぎる、人口密度が低い地域、オフィス街で夜間・休日に人通りが少ない場所など。同じ診療科のクリニックが既にいくつも存在するエリアでは、新規参入は厳しい競争を強いられます。
対策:
物件を選ぶ前に、徹底的な診療圏調査を行い、地域の人口構成、年齢層、医療ニーズ、競合クリニックの状況などを詳しく分析しましょう。公共交通機関のアクセス、駐車場の有無、周辺施設(商業施設、学校、住宅地など)との関係性も重要な判断材料です。理想的には、徒歩圏内の患者だけでなく、一定のエリアから患者を集められる立地が望ましいでしょう。ただ、診療圏調査は万能ではないともされ、将来の人口動態の変化や、ご自身のマーケティングプランも考慮に入れた長期的な視点で判断することが重要です。不動産業者だけでなく、医療専門のコンサルタントにも相談しながら、最適な物件を選ぶことをお勧めします。
コンセプトに合わない物件
クリニックのコンセプトや提供する医療サービスに合わない物件を選んでしまうことも失敗の原因となります。診療科や提供するサービスによって、必要な設備やスペースは大きく異なります。また、将来的な拡張計画や導入予定の医療機器なども考慮する必要があります。
例えば、リハビリテーションに力を入れたいのに十分なスペースがない、特定の医療機器を導入したいのに電気容量が足りない、バリアフリー対応が難しい古い建物、防音設備が不十分で周囲への騒音が心配な場所など、物件の特性がクリニックの運営に支障をきたす可能性があります。
脳神経内科やリハビリテーション科のように広いスペースが必要な診療科では、十分な面積を確保できる物件を選ぶことが重要です。逆に、内科や皮膚科など比較的コンパクトな診療が可能な場合でも、患者のプライバシーに配慮した診察室の配置や十分な待合スペースの確保が必要です。
また、医療機器の導入予定がある場合は、設置場所だけでなく、搬入経路や床の耐荷重、電気容量、空調設備なども事前に確認する必要があります。特にレントゲンやCTなどの大型機器は、設置条件が厳しく、後から変更することが困難です。
対策:
クリニックのコンセプトを明確にし、必要なスペース、設備、内装などを具体的にリストアップした上で、物件を探しましょう。建築や設備の専門家を交えた現地調査を行い、クリニックの運営に支障がないか細部まで確認することが重要です。また、将来的な拡張の可能性や、医療機器の更新・増設なども視野に入れ、余裕を持った計画を立てることをお勧めします。医療施設の設計経験が豊富な設計事務所やコンサルタントに相談することで、見落としがちなポイントを事前に把握することができます。
テナント契約における見落とし
テナントとして物件を借りる場合、契約内容を十分に確認せずに契約してしまうと、後々トラブルに発展する可能性があります。テナント契約はクリニックの運営に様々な制約を課す可能性があり、一度締結すると簡単には変更できないため、事前の確認が極めて重要です。
見落としがちなポイントとして、以下のような項目があります。
-
設備の変更可否:
新しい医療機器を設置するための床の補強や電気工事、間仕切りの変更などが可能かどうか -
ランニングコスト:
共益費や管理費の内訳、水道光熱費の負担方法、将来的な値上げの可能性 -
設備容量:
電気容量は医療機器をフル稼働させても十分か、空調設備は診療に適した環境を維持できるか -
契約期間と更新条件:
最低契約期間、更新料、中途解約時のペナルティなど -
ビルのルールや制限:
営業時間の制限、騒音に関する規制、廃棄物処理のルールなど -
広告や看板:
外観や入り口への看板設置、建物周辺での広告活動に関する制約 -
駐車場の確保:
患者用・スタッフ用の駐車スペースの有無と条件 -
バリアフリー対応:
車いすでのアクセスが可能か、エレベーターは十分な大きさか -
防音・防振対策:
医療機器の振動や音が他のテナントに影響を与えないか -
感染症対策:
換気設備は十分か、隔離スペースの確保は可能か
対策:
契約を結ぶ前に、契約書の内容を隅々まで確認し、不明な点があればオーナーや不動産業者に必ず確認しましょう。可能であれば、医療施設の契約に詳しい弁護士や不動産コンサルタントにも契約書のチェックを依頼することをお勧めします。また、現在入居している医療テナントの評判や、退去した医療テナントの理由なども事前に調査できると理想的です。契約前に、実際の開業をイメージしながら、将来発生する可能性のある問題点を洗い出し、それらが契約上どう扱われるかを確認しておくことが重要です。
人材採用の失敗
質の高い医療を提供し、患者に信頼されるクリニックを作るためには、優秀なスタッフの採用が不可欠です。しかし、医療の専門知識を持つ人材の確保は年々難しくなっており、採用から定着までのプロセス全体を見直す必要があります。特に開業当初は、経験豊富なスタッフを確保することが困難な場合が多く、計画的な採用活動が求められます。
採用基準の不明確さ
クリニックの理念や大切にしている考え方を明確にし、求める人物像(年齢、性格、スキルなど)を具体的に定義せずに採用活動を行うと、クリニックの雰囲気に合わない人材や、必要なスキルを持たない人材を採用してしまう可能性があります。採用基準が曖昧だと、面接官の主観に左右されやすく、クリニックにとって本当に必要な人材を見極めることが難しくなります。
「人柄が良い」「明るい」「真面目そう」といった主観的な印象だけで採用を決めてしまうと、実際の業務に必要なスキルや適性が不足している場合があります。医療現場は専門的な知識やスキルが求められるだけでなく、ストレス耐性やチームワーク力、患者対応力なども重要です。これらを総合的に評価するためには、明確な採用基準が必要です。
また、医療機関特有の勤務形態(夜間・休日勤務、緊急対応など)や業務内容に適応できるかどうかも重要な判断ポイントです。これらを事前に説明し、応募者の意向や適性を確認することが、ミスマッチを防ぐ上で重要です。
対策:
クリニックの理念やビジョン、求める人物像を明確にし、それに基づいた具体的な採用基準を設定しましょう。面接では、スキルだけでなく、人柄やコミュニケーション能力、クリニックの理念への共感度などを多角的に評価することが重要です。
採用したい人物像(ペルソナ)を明確化し、面接での質問項目をしっかり準備することで、感覚的な判断ではなく、客観的な評価ができるようになります。また、複数の面接官による評価や、実際の業務に近い状況での実技試験なども効果的です。特に受付スタッフや看護師は患者と直接接する機会が多いため、コミュニケーション能力の評価は慎重に行いましょう。
さらに、採用募集の段階から、クリニックの特色や求める人材像を明確に伝えることで、応募者とのミスマッチを減らすことができます。募集広告には、単に「資格」や「経験年数」だけでなく、「クリニックの理念に共感できる方」「チームワークを大切にできる方」など、人柄や価値観に関する記載も盛り込むとよいでしょう。
ミスマッチによる早期離職
採用基準が曖昧なまま採用してしまうと、クリニックの雰囲気や他のスタッフとの相性が悪かったり、仕事に対するモチベーションが低かったりするなどのミスマッチが生じ、早期離職につながる可能性が高まります。スタッフの早期離職は、採用コストや教育コストの増大につながるだけでなく、残されたスタッフの負担を増やし、クリニック全体の士気を低下させる可能性があります。
医療現場では、チームでの連携が患者ケアの質に直結するため、スタッフの頻繁な入れ替わりは大きな問題です。特に開業間もないクリニックでは、基盤となる人材の安定が重要であり、コア人材の早期離職はクリニックの成長を大きく妨げることになります。
また、医療スタッフの採用は、一般企業と比べて難しい面があります。医療資格を持つ人材は限られており、求人を出しても応募が少ないこともあります。そのため、いったん採用したスタッフが早期に離職すると、代替人材の確保に時間がかかり、その間の人手不足が患者サービスの低下を招くことになります。
早期離職の主な原因としては、以下のような要因が考えられます。
-
業務内容とのミスマッチ:
想像していた仕事内容と実際の業務が大きく異なる -
労働環境への不満:
勤務時間、休日、給与などの条件が期待と異なる -
人間関係の問題:
院長やベテランスタッフとの関係性、スタッフ間の対立やいじめ -
成長機会の不足:
キャリアアップの道筋が見えない、スキル向上の機会がない -
理念と価値観の不一致:
クリニックの方針や運営方法に共感できない
対策:
採用活動を慎重に行い、面接だけでなく、必要に応じて適性検査や体験入職などを実施し、ミスマッチを防ぐように努めましょう。採用後も、定期的な面談や研修などを通じて、スタッフの定着を促進することが重要です。
面接時には、クリニックの実情や業務内容を正確に伝え、過度な期待や誤解を生まないようにしましょう。「ホワイトな職場です」「残業はほとんどありません」などの曖昧な表現ではなく、具体的な勤務条件や職場環境を説明することが大切です。
また、採用後の教育体制も重要です。新人スタッフが安心して業務を覚えられるよう、マニュアルの整備や教育担当者の配置、段階的な業務移行など、体系的な研修プログラムを用意しましょう。特に入職後3ヶ月は離職リスクが高い時期であり、手厚いサポートが必要です。
定期的な個人面談を実施し、スタッフの不安や不満を早期に把握して対応することも有効です。単に「何か困っていることはありますか?」と聞くだけでなく、「業務で難しいと感じていることは何ですか?」「もっとこうしたらいいと思うことはありますか?」など、具体的な質問を用意すると本音を引き出しやすくなります。
理念やビジョン共有の不足
クリニックの理念やビジョンをスタッフと共有せずに採用してしまうと、スタッフはクリニックの目標や方向性を理解できず、モチベーションを維持することが難しくなります。スタッフがクリニックの理念やビジョンを共有することで、一体感が生まれ、目標達成に向けて協力しやすくなるのです。
医療機関は、単なるビジネスではなく、地域社会の健康を支える重要な役割を担っています。そのため、「患者第一」「地域貢献」「最高の医療の提供」といった理念が明確であり、それをスタッフ全員が理解・共感していることが重要です。理念への共感がないまま業務を行うと、日々の仕事が単なるルーティンとなり、やがて仕事への意欲が低下していきます。
特に医療現場では、時に困難な状況や予期せぬ事態に対応する必要があります。そのような時に、クリニックの理念が行動の指針となり、スタッフの判断や行動の基準になります。例えば、「患者さんの立場に立った医療」という理念があれば、忙しい時でも患者さんの不安に寄り添う対応が自然と実践されるようになります。
理念が明確であることは、チーム内のコミュニケーションを円滑にし、意思決定の基準を統一する効果もあります。医療は細分化された専門分野の協働で成り立っており、それぞれの専門家が共通の目標に向かって協力することが求められます。共通の理念が存在しないと、各自が異なる方向を向いて力を発揮してしまい、チームとしての成果が最大化されません。
対策:
採用面接の際や、採用後の研修などで、クリニックの理念やビジョンを丁寧に説明し、共感を促しましょう。日々の業務においても、理念やビジョンに基づいた行動を促し、スタッフのモチベーションを高めることが重要です。
具体的には、以下のような取り組みが効果的です。
-
理念を形にした「クレド」や「行動指針」の作成:
抽象的な理念を具体的な行動レベルに落とし込む -
定期的な理念研修の実施:
新人研修だけでなく、定期的に全スタッフで理念を再確認する機会を設ける -
理念に基づいた評価制度の導入:
理念に沿った行動や成果を評価し、給与や昇進に反映させる -
理念の実践事例の共有:
日々の業務の中で理念を体現した取り組みや成功事例を共有する -
院長自身が率先垂範:
経営者自身が理念に基づいた言動を心がけ、スタッフの模範となる
理念は一度決めたら終わりではなく、定期的に見直し、時代の変化や地域のニーズに合わせて更新していくことも大切です。スタッフを交えた理念の見直しは、組織の一体感を高め、理念への理解と共感を深める機会にもなります。
集患戦略の失敗
どれだけ優れた医療を提供できるクリニックでも、患者が来院しなければ経営は成り立ちません。効果的な集患戦略を立て、実行することは、クリニックの成功に不可欠です。近年では、医療機関間の競争が激化しており、単に「開業しました」という情報だけでは患者を集めることは困難になっています。
マーケティング戦略の欠如
ターゲットとなる患者層を明確にせず、どのような集患施策を展開するかの戦略がないまま開業してしまうと、患者数は伸び悩み、経営は安定しません。効果的なマーケティング戦略は、クリニックの存在を潜在的な患者に知らせ、来院を促すために不可欠です。
多くの開業医が陥りがちな誤解は、「良い医療を提供していれば自然と患者は集まる」というものです。確かに質の高い医療は重要ですが、それだけでは潜在的な患者にクリニックの存在や特色を知ってもらうことはできません。他のクリニックとの差別化ポイントや、なぜ患者がそのクリニックを選ぶべきなのかを明確に伝えるマーケティング戦略が必要です。
また、マーケティング戦略の欠如は開業場所の選定ミスにも表れます。交通の便が悪い場所や、患者層のニーズに合わない地域に開業してしまうと、いくら広告を打っても効果は限定的です。開業前のマーケティング戦略には、立地選定も重要な要素として含まれます。
さらに、開業当初は一定の広告予算を確保することが重要です。「口コミだけで十分」と考え、広告費を削減してしまうと、認知度の向上に時間がかかり、経営が安定するまでの期間が長引きます。特に新規開業の場合、最初の3ヶ月〜半年は集中的に広告宣伝を行い、認知度を高めることが重要です。
対策:
まず、ターゲットとなる患者層(年齢、性別、居住地域、疾患など)を明確にし、その層に効果的な集患方法を検討しましょう。例えば、高齢者をターゲットにするなら地域の回覧板や新聞折込、子育て世代なら子育て情報誌やSNS、ビジネスパーソンならオンライン広告など、ターゲットに合わせた媒体選定が重要です。
クリニックの強みや特色を明確にし、それを効果的に伝えるメッセージ(ブランディング)を考えましょう。「患者さんに寄り添う診療」「待ち時間の少ないクリニック」「最新の医療機器による正確な診断」など、患者が求める価値を提供していることをアピールします。
開業前から計画的にプロモーション活動を行い、開業と同時に一定数の患者が来院するような仕掛けも効果的です。例えば、内覧会の開催、地域の医療機関や介護施設への挨拶回り、開業前のホームページ公開など、認知度を高める取り組みを進めましょう。
マーケティング活動は一過性のものではなく、継続的に行うことが重要です。定期的に効果を測定・分析し、より効果的な施策に予算や労力を集中させることで、効率的な集患が可能になります。
オンライン戦略の軽視
現代において、多くの患者はインターネットで医療機関を探します。ホームページがない、情報が古い、SNSを活用していないなど、オンライン戦略を軽視していると、潜在的な患者にアプローチする機会を大きく失ってしまいます。インターネットは、潜在的な患者にとって最も重要な情報源の一つとなっています。
医療機関選びにおいて、8割以上の患者がまずインターネットで情報収集をするというデータもあります。特に若年層や子育て世代は、スマートフォンを使ってクリニック情報を調べることが一般的です。「近くの内科」「夜間診療している小児科」などのキーワードで検索し、ホームページの内容や口コミを確認した上で受診を決める傾向があります。
しかし、開業医の中には「自分の世代はインターネットをあまり使わない」「患者は病院の外観や設備で判断する」といった思い込みから、オンライン戦略を軽視するケースが見られます。これは大きな機会損失となります。現在はシニア層でもスマートフォンやタブレットの利用が進んでおり、年齢を問わずインターネット経由で情報を得る患者が増えています。
また、ホームページを作成しただけで満足し、更新を怠るケースも多く見られます。開業時の情報のまま数年放置されたホームページは、むしろマイナスの印象を与える可能性があります。定期的な更新や、検索エンジン最適化(SEO)対策が不可欠です。
さらに、SNSの活用も重要な集患戦略となっています。InstagramやX(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSを活用することで、クリニックの雰囲気や医師の人柄、提供する医療の内容などを視覚的に伝えることができます。「顔の見える医療」は患者の安心感につながり、初めての受診のハードルを下げる効果があります。
対策:
魅力的なホームページを作成し、クリニックの特色や提供する医療サービス、医師の経歴などを詳しく紹介しましょう。SEO対策を行い、検索結果で上位表示されるように努めることも重要です。また、SNSを活用して情報を発信したり、患者とコミュニケーションを取ったりすることも有効な集患手段となります。
具体的には、以下のようなオンライン戦略が効果的です。
-
ユーザーフレンドリーなホームページの構築:
スマートフォン対応(レスポンシブデザイン)、診療内容やアクセス情報の分かりやすい掲載、予約システムの導入など -
SEO対策の実施:
地域名+診療科名などの検索キーワードを意識したコンテンツ作成、Googleマイビジネスの登録・最適化 -
医療コンテンツの定期的な発信:
季節の健康情報、よくある疾患の解説、予防医学の情報など、患者に役立つ情報を発信 -
SNSの活用:
クリニックの日常風景、スタッフの紹介、健康イベントの告知など、親しみやすい情報発信 -
オンライン予約システムの導入:
24時間いつでも予約できる利便性の提供 -
口コミ管理の徹底:
Googleマップなどの口コミサイトをモニタリングし、否定的な評価には丁寧に対応
これらのオンライン戦略は、一度構築したら終わりではなく、継続的な運用と改善が必要です。可能であれば、Webマーケティングの専門家にコンサルティングを依頼するか、スタッフの中に担当者を決めて定期的に更新・管理する体制を整えましょう。