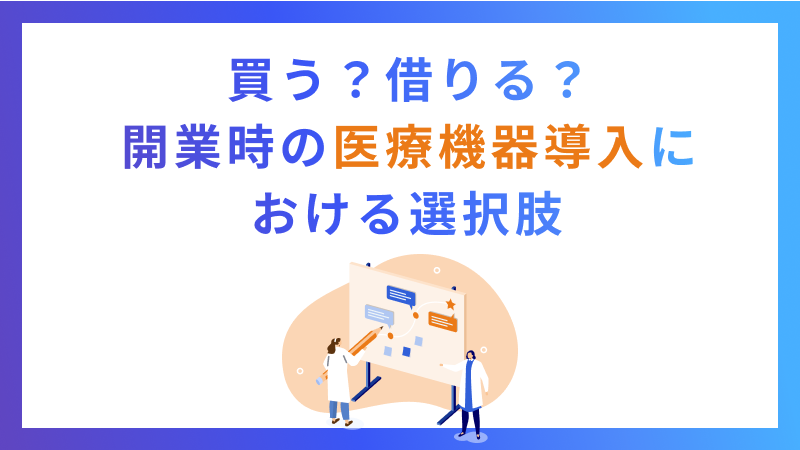
買う?借りる?開業時の医療機器導入における選択肢
開業にあたって、医療機器を導入する場合、その費用負担をどのようにしていくかは大きな悩みの種。この記事では、開業という視点から、医療機器を買うべきかリースすべきか、それぞれの長短を考察しつつ、コストパフォーマンスを検証します。
医療機器の導入、買う?リースする?
開業時の医療機器の導入では、「購入するか」「リースするか」が主な選択肢となってきます。購入は言うまでもなく、「機器をご自身で完全に所有する方法」で、長期的な使用を前提とした場合に選択されることが多くなります。初期投資は高くなりますが、使用期間が長ければコスト面で有利になる可能性があります。
リースは通常3〜7年程度の中長期契約で機器を借りる形式です。毎月のリース料を支払うため、初期投資を抑えられるのが大きな特徴です。契約期間中は継続的に使用し、期間終了後は返却もしくは買い取りをします。
どちらを選ぶかは、機器の種類や診療科の特性、予算を基に検討しましょう。高額な画像診断装置ではリースが好まれる傾向にある一方、汎用性の高い基本的な医療機器は購入を選択する医院も多いです。
リースのメリット・デメリット
医療機器をリースする場合のメリット・デメリットをより詳しく見てみると、以下の通りになります。
メリット
リースの最大のメリットは、初期費用を抑えられる点です。高額な医療機器を一括で購入する必要がないため、開業時のコストを軽減できます。例えば、1億円のMRI装置をリースで導入すれば、一度に全額を負担すること無く毎月の支払いで利用可能になります。
また、リース料は経費として計上できるため、会計処理が簡単になります。減価償却の計算や固定資産税の申告が不要で、税務面でのメリットも期待できるのが利点です。リース期間終了時に新機種への乗り換えが容易で、医療技術の進歩が速い分野では、常に最新機器を利用できる点も魅力となります。
デメリット
医療機器のリースには注意すべき点もあります。まず、契約期間中の中途解約ができないことが多いです。例えば、5年リースで3年目に機器が不要になっても、残りの期間のリース料支払いが求められることがほとんどでしょう。そのため、診療方針の変更や機器の陳腐化に柔軟に対応できない点には要注意です。
また、特別仕様や大幅なカスタマイズには対応しづらい傾向があります。標準的な仕様の機器が多いため、特殊な診療に必要な改造などは難しい場合が多いでしょう。
税務面にも注意が必要で、リースの場合は機器を資産として所有していないため、購入時に利用できる特別償却や税額控除などの優遇措置が適用されません。さらに、長期的に見ると総額が購入より高くなることも少なくありません。
購入のメリット・デメリット
医療機器を購入する場合のメリット・デメリットの詳細は次の通りです。
メリット
医療機器の購入には、長期的な視点で見たメリットがいくつかあります。まず、総額を抑えられる可能性が高いです。7年以上使用する機器では、リースより経済的になることが多いでしょう。例えば、1億円のCT装置を10年使用する場合、購入なら減価償却費のみですが、リースだと金利分で総額が膨らみます。
税制面では、条件を満たせば中小企業投資促進税制などの優遇措置が適用されます。取得価額の30%の特別償却や7%の税額控除が受けられ、初年度の税負担を大きく軽減できます。
また、自由なカスタマイズが可能な点も魅力です。特殊な診療に対応する改造や、使用方法に合わせた調整を所有者の判断で行えます。特に最先端の治療法導入時に重要な利点となるでしょう。
さらに、購入した機器は貸借対照表に資産計上できます。これにより財務内容が良くなり、金融機関からの融資を受けやすくなる可能性があります。
デメリット
医療機器を購入する際に最も大きな課題となるのは、高額な初期費用です。例えば、最新のMRI装置は1億円以上することもあり、開業時に大きな負担となります。高額な初期投資は、診療所の開業資金を圧迫し、運転資金の確保も難しくする可能性があるでしょう。
次に、機器の老朽化のリスクもデメリットです。医療技術の進歩は急速で、購入した機器が数年で陳腐化することも珍しくありません。例えば、5年前に購入したCT装置が、最新モデルと比べて画質や撮影速度で大きく劣る場合、患者の満足度や診断精度に影響を与える可能性があります。この場合、再度高額な投資が必要となり、経営を圧迫する要因になりかねません。
さらに、不要になった機器の廃棄や売却にも手間とコストがかかります。医療機器は一般的な電化製品と異なり、専門的な知識が必要な上、適切な処分方法が法律で定められています。例えば、放射線を扱う機器の廃棄には特殊な手続きが必要で、その費用も無視できません。中古市場での売却を考えても、適切な買い手を見つけるのは容易ではありません。
そのため、機器の選択は、現在の需要だけでなく、将来の診療方針や技術進歩のトレンドも見据えて慎重に行うことが大切です。
リースと購入の費用比較シミュレーション
以下は、リースと購入にかかる費用の大まかな目安です。
| 機器名 | 購入価格 | リース料 (月額) |
リース総額 (3年) |
リース総額 (7年) |
| CT装置 | 8,000万円 | 約114万円 | 4,104万円 | 9,576万円 |
| MRI装置 | 1億5,000万円 | 約214万円 | 7,704万円 | 1億7,976万円 |
| レントゲン装置 | 1,500万円 | 約21.4万円 | 770.4万円 | 1797.6万円 |
| 超音波診断装置 | 800万円 | 約11.4万円 | 410.4万円 | 957.6万円 |
| 内視鏡システム | 2,000万円 | 約28.6万円 | 1,029.6万円 | 2,400万円 |
リース期間が長くなるほど購入の方が費用負担が少なくなり、リース期間が短くなるほどリースの方がお得になります。
※リース料の計算式:月額リース料 = 購入価格 ÷ (年数 × 12ヶ月) × 1.7%
※リース料率は1.7%と仮定しています(実際は契約により異なります)
※購入の場合、減価償却費や保守費用は含まれない想定です
※リース料には保守費用が含まれる想定です
リースか購入かを検討する際に目を向けるべきポイント
医療機器をリースか購入かを判断する際には、まず機器の耐用年数を考慮しましょう。一般的に、7年以上使用する見込みの機器は購入が有利です。例えば、基本的な検査機器やレントゲン装置などは、長期使用が想定されるため購入を検討すべきでしょう。一方、5年程度で更新が必要な機器はリースが適している可能性が高いです。
次に、モデルチェンジやバージョンアップの頻度を確認します。技術革新の速い分野の機器、例えば内視鏡システムや超音波診断装置などは、数年で新機種が登場することも珍しくありません。こうした機器はリースを選択することで、常に最新技術を導入できる利点があります。
設置環境も重要な判断基準です。大型機器を購入する場合、将来的な移設やレイアウトの変更の可能性も考慮する必要があります。リースであれば、契約終了時に返却可能なため、より柔軟な対応が可能です。例えば、CT装置を導入する際、将来的に診療所を拡張する計画がある場合はリースが有利でしょう。
メンテナンスとサポートの充実度も確認が必要です。購入の場合、長期的なメンテナンス契約や緊急時のサポート体制を個別に確保する必要があります。一方、リースでは包括的なサポートが含まれていることが多く、特に高度な技術サポートが必要な機器では大きなメリットとなります。
このように、リースか購入かは費用だけでなく将来的な機器変更なども考慮して決定するのがポイントです。
リース契約の流れ
医療機器のリース契約は、以下のような流れで進行します。
1. 機器の選定と条件交渉
医療施設と販売元が機器の種類、仕様、価格、納入時期などを決定
2. リース申請
リース申込書と直近2期分の財務資料をリース会社に提出
3. 審査プロセス
リース会社が申請内容を精査
4. 契約締結
審査結果を踏まえ、リース契約を取り交わし
5. 発注手続き
リース会社から販売元に機器を発注し、売買契約を締結
6. 納入とリース開始
販売元が医療施設の指定場所に機器を配送し、リースを開始
7. リース料の支払い
初回と前払い分をリース開始時に支払い、以降は毎月同額を支払い
8. 機器の保守管理
医療施設と販売元間で保守契約を締結