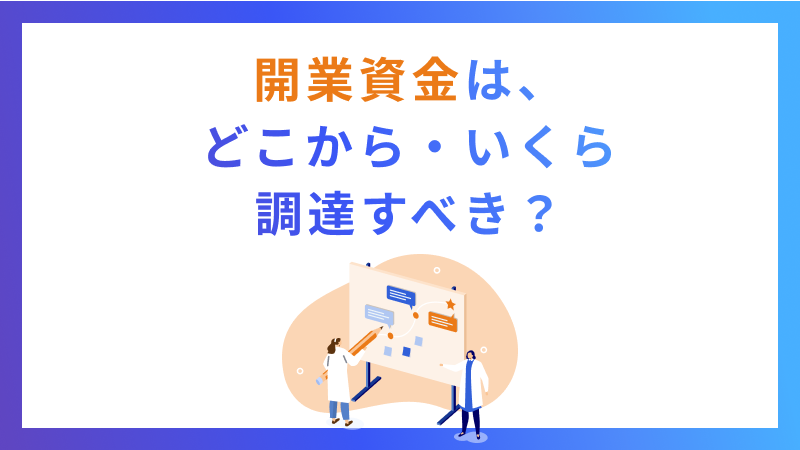
開業資金は、どこから・いくら調達すべき?
開業資金は、どこから・いくら調達すべき?
クリニック開業には相当な資金が必要となります。一般的に、開業資金の総額は1億円から3億円程度と言われていますが、立地や規模、診療科目によって大きく変動します。例えば、都心部での開業や高額な医療機器を必要とする診療科では、さらに高額になる可能性があります。
40坪の物件で内科開業すると仮定すると、必要な資金の大まかな目安は以下の通りです。
| 開業に必要な費用例 | 費用感 |
| 賃貸借契約関連 | 2万円×40坪×12ヶ月=960万円 |
| 設計施工 | 70万円×40坪=2,800万円 |
| 医療機器・電カル | 1,200万円程度 (X線、CR、エコー、POST、電子カルテなど) |
| 運転資金 | 2,000万円〜 (販管費×6か月+院長の生活費) |
| 合計 | 7,000万円+α |
資金調達の方法
融資による資金調達
融資による資金調達が最も一般的な方法です。主に公的金融機関や民間金融機関から借り入れを行います。銀行や公的金融機関で開業のための融資を受ける際には必ず事業計画書が必要になります。なお、
銀行による医師向けの融資にもいくつか種類があり、メガバンクなどが取り扱っている診療所向けの融資パッケージ商品は、審査が厳しくない一方で利率が少し高めになっています。公的金融機関においても借入金額に制限があったり、利率が高かったりと、各銀行によって審査基準や基準の利率はさまざま。2~3行に相談して利率や条件を比較するのが良いでしょう。
自己資金
最も安全で確実な資金調達方法です。金利負担がなく、返済の心配もありません。ただし、多額の資金を用意するのは容易ではないため、他の方法と組み合わせて使うことが多いです。開業時の自己資金は総額の20%程度が目安とされています。
ご希望次第ですが、余裕がない限りは資金投入せず、万一のために手元に資金を持っておくのも一つ。そもそも銀行の利率が比較的高くなく、また万一開業後に資金が不足してしまった場合に追加融資を受けることは簡単ではないため手元資金には余裕を持たせて置く必要があるためです。この辺りの計画も先生の希望や銀行の条件にもよりますので、ご自身の計画を踏まえ、専門家に相談するとよいでしょう。
親族や知人からの資金提供
身近な人からの資金提供は、条件が柔軟で借入れやすい利点があります。しかし、後々のトラブルを避けるため、返済計画は明確にし、できれば契約書を交わしておくことをおすすめします。
| 資金調達方法 | 説明・特徴 | 考慮点 |
| 【1】自己資金 | 貯蓄から開業費用を捻出する。 |
〇:手続きの負担や手数料・利息がない 〇:返済不要のため、開業後の負担が軽い ×:開業後の手元資金不足に注意する |
| 【2】親族間借入 | 親族から借りる。一般的には税理士に相談しながら進める。 |
〇:交渉次第で返済計画を柔軟に決められる ×:贈与判定に注意、無利子はNG ×:家族トラブルのリスクあり |
| 【3】金融機関・他借入 | メガバンク、地銀、日本政策金融公庫、医師会の系統などで審査基準や条件が異なる。 |
〇:無理のない借入内容・返済計画を提案されるため安心 ×:審査あり、借入条件あり |
| 【4】リース |
自己資金や他借入と併せて検討することが多い。 医療機器に特化した「リース会社」もあるため先に金融機関と相談するのも◎ |
〇:【1】〜【3】にプラスして資金調達額を確保できる ×:対象物が動産(医療機器など)に限定される ×:【3】の利息と比較してリース料が高くなることが多い ×:リース期間後も再リースとなるケースが多く、要確認 |
主たる融資元
日本政策金融公庫
国民生活事業での融資が主で、新規開業資金や女性、若者/シニア起業家向けの支援資金などがあります。比較的低金利で、長期の返済期間が設定できる利点があります。
民間金融機関
地方銀行、都市銀行、信用金庫などが該当します。地域密着型の融資や、独自の医療機関向け融資商品を提供していることもあります。
独立行政法人福祉医療機構(WAM)
医療機関向けの融資を専門に行う公的機関です。長期・固定金利で安定した借入が可能です。医療機関の特性を理解した融資条件が設定されています。
医師信用組合
医師や歯科医師を対象とした金融機関です。医療業界に特化しているため、開業資金の融資に関する相談や助言も得られやすいでしょう。
主な借入先の特徴
| メガバンク | 地方銀行 | 日本政策公庫 | 医師信用組合 | |
| 融資金額(上限) | △~〇 | △~〇 | △ | 〇〜◎ |
| 金利 | 〇 | ◎ | △ | ◎ |
| 担保無プランの有無 | 応相談 | あり | あり | 応相談 |
| 返済年数(目安) |
設備:~10年 運転:~10年 |
設備:~15年 運転:~10年 |
設備:~20年 運転:~7年 |
設備:~20年 運転:~20年 |
| 手続きの煩雑さ | 〇 | 〇 | △ | △ |
| 利便性 | ◎ | △~〇 | △ー | ー |
※地方銀行:各都道府県の第一地銀ほかを想定
資金調達のための事業計画書の書き方
資金調達のための事業計画書では、主に以下の内容の記入が必要です。
収支計画書
収支計画書に記載する代表的な項目は下記になります。
<収入>
- 患者見込み計画書にも基づく収入予測
<支出>
- 人件費
- 賃料
- 減価償却費(リース料)
- 借入金の返済額
診療圏調査などの結果から得られた患者見込みに診療単価を掛けた収入から、人件費、賃料などの固定費と借入金の返済額を差し引いた収支を記載する書類が「収支計画書」です。この収支計画書が事業計画書の中でも最も重要になります。
開業後数カ月は計画通りの患者数が見込めないので、当面の資金繰りと、軌道に乗った後の損益計算書は別々に検討することをお勧めします。開業当初に資金がショートしないよう、毎月最低でも1,000万円の手元資金を確保すべきとされてきましたが、最近では競争環境が厳しくなってきており、2,000万程度が手元に残るよう可能な限り借入をする必要があるという指摘も増えてきました。
また、軌道に乗った後の損益計算書は楽観的、通常、悲観的の3パターンを作成すると、固定費の大部分を占める人員計画などを立てる際に参考になります。
患者見込み計画書
患者見込み計画書は、開業支援企業が行っている診療圏調査の結果で得られる、1日あたり来院する患者の数を参考にするのが一般的です。診療所の収入は下記で表すことが可能です。
診療所の月収=1日当たりの患者の数×平均診療単価×診療日数
ただ、いわゆる上記の数値も重要ですが、開業予定地の患者の層の現状と今後の変化と、近隣の競合医院の先生の年齢や後継者の有無などどれだけ精度の高い情報を把握しているかが事業計画には重要になります。
設備計画書
「設備計画書」に記載するのは、基本的に初期投資です。具体的には物件の賃料や保証金、建築、内装費、医療機器などがあたります。初期投資では内装費のウエイトが大きくなります。医療機器も設備に該当しますが、手元の資金に応じて購入かリースか選択することになります。リースの場合はトータルで支払う額は多くなりますが、毎月少額のリース料だけで医療機器を使用できる点がメリットとなります。
担保明細
担保明細は不動産の場合は登記簿謄本が必要になります。保健所や厚生局に事業計画書を提出する場合は、同時に必要書類として、賃貸物件の場合は賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書が必要になる場合もあります。ただ、近年では保証人・担保不要の借入も増えています。
クリニック開業資金の節約方法
まず物件選びでは、駅前や繁華街から少し離れた場所を検討することで、賃料を大幅に抑えられます。例えば、駅から徒歩10分程度の場所を選ぶことで、駅前と比べて賃料を抑えられる可能性があります。ただし、クリニックへのアクセスの良さとのバランスは慎重に検討しましょう。
内装工事では、過度に凝ったデザインを避け、機能性を重視することで費用を抑制できます。例えば、受付カウンターや待合室の椅子などは、既製品を活用すると節約になります。また、将来の拡張を見越して、段階的に内装を整えていく方法も効果的です。
医療機器は、リースやレンタルの活用、中古品の購入も選択肢に。特に、高額なレントゲン装置やCTスキャナーなどは、リースを利用することで初期投資を大幅に抑えられます。ただし、診療に直結する重要機器は新品を選ぶなど、質と価格のバランスを見極めることが大切です。メーカー保証切れやその他トラブルを避けるため、中古品を利用する場合は細心の注意を払いましょう。
広告宣伝費は、開業時に大きくなりがちですが、SNSやホームページなどの低コストな媒体を中心に活用することで抑制できます。例えば、FacebookやInstagramでの情報発信、地域のコミュニティサイトへの投稿など、費用をかけずに地域住民へアプローチする方法も。医療モールで開業する場合は内覧会をモール合同で開催できるため、印刷費やポスティング費用を抑えられることがあります。
これらの方法を組み合わせることで、開業資金をある程度節約できるでしょう。ただし、過度な節約は診療の質や患者サービスの低下につながる恐れがあるため、バランスを取ることが重要です。長期的な視点で、必要な投資と節約のバランスを見極めましょう。