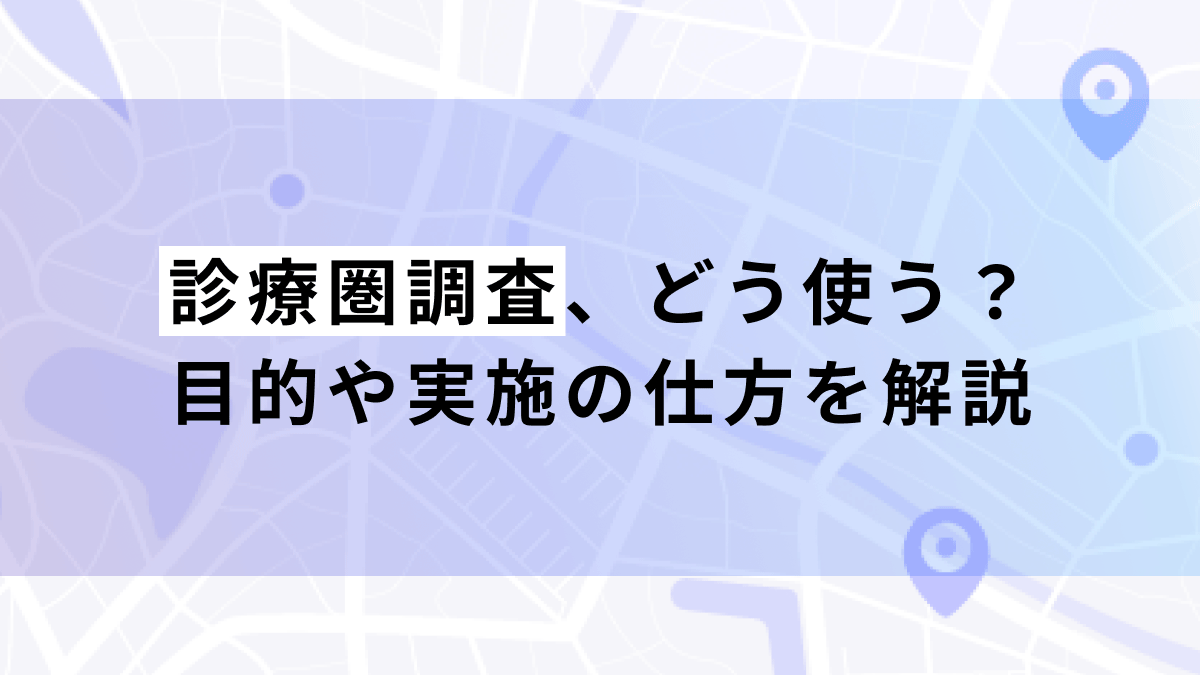
診療圏調査、どう使う?目的や実施の仕方を解説
医院開業時、立地を考える時によく目にする「診療圏調査」。その土地に開業したことでどの程度の集患が見込めるかを分析するためには有用だと言われますが、患者の受診動態も複雑化している現在では、「診療圏調査をやってもなかなか生かし切れない」という声も聞くのが実情です。この記事では、そもそも診療圏調査の目的にも立ち返りつつ、その活用法や、診療圏調査と向き合う上でのポイントについて解説します。
診療圏調査とは
診療圏調査とは、開業予定のエリアにおける医療需要と供給のバランスを把握するための調査です。
地域内の人口動態や年齢層、競合クリニックの状況、患者の動向などを分析し、クリニック開業の成功可能性を評価するために行われます。診療圏調査の結果に基づいて、どの地域で開業すべきか、どの診療科目が不足しているか、競合クリニックとの差別化ポイントは何かを明確にすることができます。
診療圏調査は、医療物件の選定において、成功するための重要な工程と言え、開業を検討している医師にとっては、開業後の集患力や経営の安定性に直結します。
診療圏調査のそもそもの目的
診療圏調査の主な目的は、開業予定エリアの医療需要を把握し、その地域で成功する可能性が高いかどうかを判断することです。これにより、開業するクリニックのターゲットとなる患者層や、その地域の競合状況をある程度把握することができます。
診療圏調査を行うことで、以下のような具体的な情報を得ることが可能です。
- 地域の人口構成(年齢分布や人口密度)
- 競合クリニックの数と診療内容
- 周辺の医療供給体制(病院や専門クリニックの有無)
- 患者の通院傾向や移動手段
これらのデータは、開業後のクリニック経営を支える重要な指標となります。ただ、昨今の患者の受診動態はそう単純でもありませんし、診療圏調査にはいくつかの落とし穴も存在します。「意味はあるが、万能ではない」という前提をもって向き合う必要があり、そのうえでのポイントを解説します。
診療圏調査の落とし穴
診療圏調査は非常に有効なツールではありますが、いくつかの落とし穴も存在します。調査結果に依存しすぎることで、思わぬリスクに直面することもあります。以下では、代表的な診療圏調査の課題について解説します。
競合の存在を考慮しにくい
診療圏調査は、競合クリニックの数や診療内容を把握するのに役立ちますが、競合の実際の影響力や集患力を正確に反映できない場合があります。競合クリニックが後から増え、患者数が減少してしまうケースもあり得ますし、競合クリニックが提供する医療の質や患者へのサービス、立地条件などの要素は、数値だけでは測れない複雑な要素です。特に、長年にわたって地域に根付いているクリニックや、患者との関係性を築いている医師がいる場合、その競合の影響は大きくなることがあります。
患者の受診動態が複雑化している
診療圏調査は通常、地域住民の受診傾向を基にデータを収集しますが、最近では患者の受診動態が多様化・複雑化してきています。たとえば、都市部では、患者が自宅近くのクリニックではなく、通勤途中や職場近くのクリニックに通うケースが増えています。さらに、オンライン診療が普及したことで、地理的な制約が緩和され、必ずしも近隣のクリニックを選ぶわけではない状況も生まれています。
これにより、診療圏調査が想定する「地域の医療需要」が実際の受診行動と乖離してしまうことがあり、予想外の集患難に直面するリスクが存在します。
都市計画など外部要因で事情が変わる
都市部では再開発や新しい商業施設の建設、交通インフラの整備などの都市計画が進行中の場合、診療圏調査で得られた情報が短期間で陳腐化する可能性があります。資料でも、「駅近で開業して集患に成功したが、その後近隣に新しい医療モールができたため、競合が激増し、患者数が減少した」という事例が挙げられています。
このように、都市計画や開発状況といった外部要因は、診療圏調査の結果には含まれにくいものの、経営に大きな影響を与える要素です。そのため、定期的に外部要因を確認し、柔軟に戦略を調整することが求められます。
診療圏調査、どこまで信じてもいい?
このように診療圏調査は、クリニック開業のリスクを軽減し、成功の可能性を高めるために欠かせないツールですが、開業を成功させるためのすべての因子を網羅しているわけではなく、万能ではありません。データを過信せず、補完的な要素を加味しながら、ご自身の感覚も踏まえてバランスよく活用することが大切です。ここでは、診療圏調査をどこまで信頼すべきか、どのように活用するべきかについて説明します。
適切に補正をする
診療圏調査のデータは、あくまで地域の平均的な状況を示すものです。そこで得られるデータは、そのまま信じるのではなく、自分のクリニックのコンセプトや診療科目に応じて適切に補正する必要があります。たとえば、診療圏内に若年層が多くても、開業予定の診療科目が高齢者をターゲットにしている場合、データをそのまま受け取ってしまうと誤った結論に至る可能性があります。
競合の存在も意識しながら考察する
競合状況は、診療圏調査のデータを正確に反映しきれない要素の一つです。競合クリニックが提供するサービスの質、立地条件、患者の信頼度などは、数値化しにくい要素です。競合が多いエリアでは、「立ち上がりが良好だったが、その後ライバルが増えて患者数が減少した」という事例もあり、競合の存在感をどこまで意識すべきかは、現場の肌感覚がある程度は求められます。
時間帯(夜間・人口)を加味して考える
診療圏調査では、通常の診療時間に基づくデータが多くなりますが、夜間診療や休日診療を行う場合、異なる患者層が集まる可能性があります。夜間に活動する職業やシフト勤務の患者など、通常の診療圏調査では見落とされがちな層を考慮することが、集患の成功につながる場合もあります。
住民の意識や価値観を考慮する
地域ごとの住民意識や文化も、診療圏調査では数値化しにくい要素といえます。たとえば、医療に対する意識が高く、先進的な医療技術を求める患者が多い地域では、新しい設備や治療法を導入することが成功につながるかもしれません。一方で、保守的な地域では、伝統的な診療スタイルを維持することが求められることもあります。こうした土地柄としての背景を認識し、数値データに頼りすぎない判断が重要です。
診療圏調査は、クリニック開業の際に重要なツールですが、その結果を過信せず、現場の状況やその他の要素を考慮することが必要です。診療圏調査を補完する形で、開業予定エリアの文化や住民の意識、さらには競合の動向など、数値化しにくい要素も見逃さないようにすることで、より正確なエリア選定が可能となります。
「意味はあるが、万能ではない」前提で向き合う
診療圏調査は、クリニック開業を成功させるための有益なツールですが、その結果に頼りすぎるのは危険です。データをもとにした計画はもちろん重要ですが、それだけでは見えない要素をしっかりと把握し、補完的な情報を組み合わせることが求められます。
診療圏調査は、あくまで一つのガイドラインとして捉え、自身の診療科目や患者層に合わせた補正を行い、地域の特性を深く理解しながらエリア選定を進めることで、安定した経営と集患の成功が見込まれます。さらに、診療圏調査で見えてくる情報を基にしつつも、地域の文化や住民のニーズに柔軟に対応することで、開業後の成功に繋がるエリア選定ができるでしょう。